SNSでどの記事を宣伝すべき?PVが多い記事と少ない記事、賢い使い分け方【ブロガー必見】
ブログ記事が増えてくると、SNSでどの記事を紹介するべきか迷う瞬間がありませんか?
「PVが多い記事をさらに伸ばすべき?」「伸びていない記事をSNSで押し上げるべき?」──。
どちらを優先するかで、SNS運用の成果は大きく変わります。
本記事では、400記事規模のブログを運営する中で見えてきた、
「PVが多い記事」と「少ない記事」をSNSでどう使い分けるかの具体的な戦略を解説します。
X(旧Twitter)で反応が取れる投稿の法則から、
低PV記事を“育てる”ための導線設計まで、実践的なノウハウをデータ視点でまとめました。
「SNSを頑張っているのに成果が出ない」「どの記事を宣伝すべきか毎回悩む」
──そんなブロガーの方に、**今日から使える“投稿優先度の考え方”**をお届けします。
筆者注:
おかげさまで、現在運営している2サイトの合計PVが2025年11月時点で約9万PVに到達しました。
10万PVはあくまで通過点と捉え、2026年には20万PVの達成を目指して運用を加速しています。
その過程で直面したのが、**「アクセスされる記事と、されない記事をどう扱うべきか」**という問題。
本記事では、その具体的な考え方とSNSでの活かし方を整理してまとめました。
🟩 H2-1:なぜ「SNSでどの記事を宣伝するか」が重要なのか
- H3-1:SEOだけではPVが伸びにくい時代に突入
- H3-2:SNSは“読まれるきっかけ”を作る場所
- H3-3:「記事選定」が間違っていると、どれだけ投稿しても伸びない
💡導入パートでは、あなた自身の「耳スタ400記事」や「PV分布(上位記事と下位記事の差)」を例に出すとリアルさが伝わります。
🟩 H2-1:なぜ「SNSでどの記事を宣伝するか」が重要なのか
ブログ記事をSNSで紹介するとき、ただリンクを貼るだけでは思ったようにPVは伸びません。
実は、「どの記事を選んで投稿するか」で、SNSからの流入効果は大きく変わります。
SEOと違い、SNSは“読まれるきっかけ”を能動的に作り出せる場。
だからこそ、投稿対象の選び方が戦略の中心になります。
🟨 H3-1:SEOだけではPVが伸びにくい時代に突入
近年の検索環境は、AI要約や自動回答の登場で「検索→クリック→ブログ閲覧」という流れが少しずつ減っています。
いくら良質な記事を積み重ねても、SEOだけで安定したアクセスを維持するのは年々難しくなっています。
そこで再注目されているのがSNS、特にX(旧Twitter)です。
SNSは、検索順位に左右されずに記事を読んでもらえる**“第二の入口”**。
SEOで拾われないキーワードや共感ネタでも、SNSでは読者のリアルな興味関心で拡散されるため、PVの下支えと新規読者の獲得につながります。
🟨 H3-2:SNSは“読まれるきっかけ”を作る場所
SNSの本質は「拡散」よりも「接点づくり」です。
ユーザーは記事タイトルで検索するのではなく、タイムラインで偶然目にする投稿から興味を持ちます。
つまりSNSは、読者にとって「知らなかった記事を知るきっかけ」なのです。
この段階では、“どんな記事を出すか”が極めて重要。
PVが多い記事を出せば確実に反応が取れ、低PVの記事でも切り口を変えれば新しい層に届くチャンスがあります。
SNSの投稿は1回きりではなく、**「読者とのタッチポイントを増やすための再放送」**と捉えるのが正解です。
🟨 H3-3:「記事選定」が間違っていると、どれだけ投稿しても伸びない
SNS運用がうまくいかない最大の理由は、「どの記事を出すか」があいまいなこと。
人気記事を出しすぎて飽きられたり、逆に誰も知らない低PV記事ばかり出して反応が薄かったり…。
記事選定の目的は、“バズ”ではなく“継続的な流入”です。
反応率が高い上位記事でまずアカウントの信頼を積み上げ、
そのあとで関連する中堅・低PV記事を内部リンクで紹介する。
この流れを作ることで、SNS発信が単発ではなく、ブログ全体のPVを押し上げる導線に変わります。
🟩 H2-2:まずは自分のブログを“PV分布”で可視化しよう
- H3-1:PVが多い記事/少ない記事を分類する(例:200PV以上・50PV以下)
- H3-2:PVが少ない=悪い記事ではない理由
- H3-3:「伸びる余地がある記事」をどう見つけるか
🧠ここはデータ分析の導入。GSCの「クリック数×表示回数」で例を示すと説得力が増します。
🟩 H2-2:まずは自分のブログを“PV分布”で可視化しよう
SNSでどの記事を宣伝すべきかを判断するには、まず**「どの記事がどれくらい読まれているか」**を整理することから始めましょう。
闇雲に投稿しても効果は出ません。
数字をもとに「上位・中堅・下位」を明確に分けることで、SNS投稿の優先順位が見えてきます。
🟨 H3-1:PVが多い記事/少ない記事を分類する(例:200PV以上・50PV以下)
Googleアナリティクス(GA4)やSearch Consoleを使って、直近30〜90日間のPVデータを確認します。
ざっくりとした目安でかまいませんが、たとえば次のように区分すると効果的です。
| 区分 | PV目安 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 上位記事 | 200PV以上 | SNSでも主力として推すべき“花形記事” |
| 中堅記事 | 50〜199PV | 改善次第で上位入りを狙える“育成候補” |
| 低PV記事 | 〜49PV | 投稿・内部リンクの見直しが必要な“再設計ゾーン” |
数字はブログ規模によって変わりますが、
このように階層化すると「どの記事をSNSで出すべきか」「どの記事を育てるか」がはっきりします。
耳スタでも、400記事のうち約70〜80本が200PV以上あり、
このゾーンの記事がSNS発信の中心軸になっています。
🟨 H3-2:PVが少ない=悪い記事ではない理由
PVが少ない記事は“失敗作”ではありません。
単に「露出の機会が少ないだけ」というケースが非常に多いのです。
特に次のような記事は、内容が良くても検索流入に恵まれていない隠れた良記事かもしれません。
- 検索ボリュームの少ないニッチキーワードを狙った記事
- 内部リンクが貼られていない記事
- 投稿から日が浅く、まだGoogleに十分評価されていない記事
SNSは、こうした“まだ発見されていない記事”に光を当てる絶好のチャンスです。
リライトや再投稿で、見せ方を変えれば一気に読まれる記事へ変わることもあります。
🟨 H3-3:「伸びる余地がある記事」をどう見つけるか
PVが低くても、表示回数が多い記事=伸びしろがある記事です。
Search Consoleで「クリック数」「表示回数」「CTR」を並べて見てみましょう。
- 表示回数が多く、クリック率が低い → タイトル・ディスクリプション改善の余地
- 表示回数が少ないがCTRが高い → ニッチだけど強いキーワード。SNS発信で一気に拡散できる可能性あり
また、SNSでは「共感」や「話題性」が大きな武器になるため、
数字だけでなく“人の感情が動くテーマ”かどうかも判断基準に入れましょう。
耳スタでは、検索順位が高くなくても「ユーザーが疑問を感じやすい記事(例:イヤホンのペアリングトラブル)」をSNSで紹介したところ、
短期間で数百PVアップするケースもありました。
🟩 H2-3:PVが多い記事は「SNSの主力コンテンツ」にすべき理由
- H3-1:SNSアルゴリズムは“反応率”が命
- H3-2:人気記事は拡散しやすく、他記事の信頼性も底上げ
- H3-3:「何度も投稿していい」—Xで繰り返し出すメリット
📈例:「ダイソーイヤホン記事」などの投稿文例を紹介してもOK。
(→このパートで投稿文テンプレを添えると読者が保存します)
🟩 H2-3:PVが多い記事は「SNSの主力コンテンツ」にすべき理由
SNS運用でまず優先すべきは、すでに反応が出ている記事=PVが多い記事です。
なぜなら、SNSでは投稿そのものの“反応率”がアルゴリズムに強く影響し、
初動でいいね・クリック・滞在が多い投稿ほど多くの人に表示されやすくなるからです。
PVが多い記事は、すでに検索経由で評価を得ている「読まれる力」を持っています。
SNSで拡散することでさらに勢いを増し、他の記事の信頼性までも押し上げる効果が期待できます。
🟨 H3-1:SNSアルゴリズムは“反応率”が命
X(旧Twitter)では、投稿がユーザーのタイムラインにどれだけ表示されるかは初動の反応率で決まります。
つまり、最初の数分〜数時間で「いいね」や「クリック」が集まらない投稿は、ほとんど拡散されません。
そのため、SNSでは“反応が取れやすい記事”を選ぶことが重要です。
PV上位の記事は、すでに検索読者に支持されている=内容の信頼性が高い記事。
それを投稿すれば、自然にCTR(クリック率)やエンゲージメント率が高まり、アルゴリズム的にも優遇されます。
特に次のような記事は、SNS向きの“反応を呼ぶ素材”です。
- タイトルが感情に刺さる(「コスパ最強」「初心者でも安心」など)
- 図解・写真などビジュアル要素がある
- 一言コメントを添えやすい(「これ、本当に便利でした!」など)
SNSはアルゴリズムが支配する世界ですが、その仕組みを理解して「読まれやすい記事を出す」ことが成功の第一歩です。
🟨 H3-2:人気記事は拡散しやすく、他記事の信頼性も底上げ
PV上位の記事をSNSで発信するもう一つの理由は、ドメイン全体の信頼性(EEAT)を底上げできることです。
SNS経由で多くのユーザーがアクセスすると、Googleは「外部からの関心が高い記事」と認識しやすくなります。
結果として、他の記事の評価にも好影響を与えるケースがあります。
さらに、SNS上で人気記事を繰り返し紹介すると、フォロワーの中で
「あのアカウント=信頼できる情報源」という認知が形成されます。
このブランド効果がつくと、低PV記事を紹介したときもクリック率が上がるという好循環が生まれます。
実際に耳スタでも、ダイソーイヤホンやLDAC系の記事を繰り返しSNSで出すことで、
同カテゴリーの新記事(まだ数十PVレベル)にも自然流入が増える現象が確認できました。
🟨 H3-3:「何度も投稿していい」—Xで繰り返し出すメリット
SNSで同じ記事を何度も投稿することに抵抗を感じる人もいますが、
Xのタイムラインは常に流れ続けるため、同じ投稿を再発信してもほとんどの人は気づきません。
むしろ、時間帯・コメント・切り口を変えて繰り返し投稿することで、
異なる層に届くチャンスが増えます。
たとえば:
- 朝:通勤前に読む層向けに「初心者向けの安心ポイント」を強調
- 夜:リラックスタイム向けに「コスパ最強イヤホンまとめ」として再投稿
- 週末:買い物モードの層に「この価格でこの音質、見逃さないで!」
このように投稿角度を変えれば、1記事で3〜5回分の露出を作ることが可能です。
SNSの世界では、“質より量”ではなく、“同じ良質コンテンツを角度を変えて届ける量”が成果を左右します。
🟩 H2-4:PVが少ない記事をSNSでどう扱う?賢い“育成戦略”
- H3-1:直接宣伝より“人気記事経由”で誘導する
- H3-2:リライト→再投稿で反応率を計測
- H3-3:カテゴリやシリーズでまとめて紹介する
🪄ここで「人気記事+関連リンク」形式の投稿例を提示すると実用的です。
🟩 H2-4:PVが少ない記事をSNSでどう扱う?賢い“育成戦略”
PVが少ない記事をSNSでどう見せるか——これは多くのブロガーが悩むポイントです。
しかし、結論から言えば「低PV記事こそSNSと相性が良い」場合があります。
SNSは“知るきっかけ”を与える場所。
検索で埋もれている記事をSNSで掘り起こすことで、まったく新しい層に届くことがあるのです。
ただし、闇雲に投稿しても反応は得られません。
ここでは、PVの少ない記事を効果的に育てていく3つの戦略を紹介します。
🟨 H3-1:直接宣伝より“人気記事経由”で誘導する
低PV記事を単体で投稿すると、クリック率が上がりづらく、SNS上のアルゴリズムにも乗りにくい傾向があります。
そこでおすすめなのが、「人気記事+関連リンク」形式の投稿です。
たとえば、次のように構成します👇
🎧【ダイソーイヤホン比較】人気No.1のG273-3とG273-4、どっちが買い?
詳細レビューはこちら👉 https://earbuds.aspsv.com/2025y-daiso-comp4112/
(※初めての方は説明書ガイドもチェック)
👉 https://earbuds.aspsv.com/daiso-wireless-earphones-manual-detailed-guide/
このように、まず“読まれやすい記事”を入口にして、その下で低PV記事を補足として紹介します。
クリックされやすく、内部導線の自然流入も同時に増やせるため、SNSとSEOの両面で効果が出やすい構成です。
特に「補足情報」「詳しい手順」「体験談」としてつながる記事は、組み合わせ投稿に最適です。
🟨 H3-2:リライト→再投稿で反応率を計測
PVが伸びない記事は、投稿前に**軽くリライトして“再挑戦”**しましょう。
Xで反応を取るには、タイトル・1行目の印象がとても重要です。
たとえば、
「LDAC接続できないときのチェック方法」
というタイトルを、
「音が出ない?LDACが有効にならないときの“3つの確認ポイント”」
といった形にリライトして投稿すると、CTRが数倍に伸びることもあります。
さらに、再投稿後の反応率(いいね・クリック数)を小さく計測しておくと、
「リライト前より反応が上がった/下がった」が判断でき、次の改善につなげやすくなります。
SNSは“テストの場”でもあるので、反応データを仮説検証の材料として使うと、
記事全体のクオリティを上げるヒントが得られます。
🟨 H3-3:カテゴリやシリーズでまとめて紹介する
低PV記事を単独で出すより、シリーズ化してまとめ投稿するのも有効です。
読者にとって「関連性がある」と感じられるとクリック率が上がります。
たとえば、耳スタなら👇
📚【骨伝導イヤホン特集】
① 仕組みをやさしく解説 → https://earbuds.aspsv.com/bone-conduction-howitworks/
② 聞こえ方の特徴と注意点 → https://earbuds.aspsv.com/bone-conduction-merit-demerit/
③ おすすめモデルまとめ → https://earbuds.aspsv.com/bone-conduction-best2025/
このようにカテゴリで束ねて紹介すれば、複数記事をまとめて露出できます。
1投稿あたりのリーチが広がるだけでなく、
「この人は専門的に発信している」という認知が強まり、フォロワーの信頼度も上がります。
また、週末やキャンペーン時などに「テーマ投稿」として再掲すると、
過去記事の掘り起こしにもつながります。
🟩 H2-5:SNS運用で意識すべき“3層構造”の投稿設計
- H3-1:花形記事(PV1000〜)=ブランド訴求・新規流入
- H3-2:中堅記事(PV200〜500)=ファン維持・深掘り導線
- H3-3:低PV記事(〜100)=内部リンクで育成
📊 このパートで「投稿比率:主力6/中堅3/低PV1」など黄金比を示すと、記事の信頼度がぐっと上がります。
🟩 H2-5:SNS運用で意識すべき“3層構造”の投稿設計
SNSで記事を投稿するときに、すべての投稿を同じように扱ってしまうと、成果が伸び悩みます。
実際には、記事のPVや役割によって投稿目的を分けることが大切です。
ブログを「花形」「中堅」「低PV」の3層で整理し、それぞれの役割を意識した投稿を組み合わせることで、
SNS発信全体の“導線バランス”が整い、安定したPV増加につながります。
🟨 H3-1:花形記事(PV1000〜)=ブランド訴求・新規流入
花形記事は、あなたのブログの「顔」となる記事。
SNSではブランド認知と新規読者の獲得を目的に、定期的に発信しましょう。
- 例:耳スタの「ダイソーイヤホンおすすめ5選」「LDAC対応スマホ一覧」など
- 投稿比率の目安:全体の50〜60%
花形記事を出すと、フォロワー以外の層にも広がりやすく、
「このアカウント=信頼できる情報源」としての印象を強めます。
また、初見の読者がプロフィールからサイト全体へ流れやすくなるため、
**アカウントの成長スピードを加速させる“フロントエンジン”**の役割を持ちます。
投稿のポイントは、「人気記事を何度も角度を変えて出す」こと。
1回きりではなく、朝・夜・週末で切り口を変えることで、読者層を広げられます。
🟨 H3-2:中堅記事(PV200〜500)=ファン維持・深掘り導線
中堅記事は、花形記事で集まった読者を“さらに深掘り”へ導く役割を持ちます。
SNSでは、信頼の積み上げと滞在時間の増加を狙いましょう。
- 投稿比率の目安:全体の30〜40%
- 投稿目的:読者の理解・共感を深めて、リピーターを育てる
たとえば、LDACピラーページから派生した「WindowsでLDACを使う方法」や
「GalaxyでLDACが有効化できない時の対処法」などがこの層に該当します。
これらの記事は“新規読者向け”ではなく、既にあなたの情報に信頼を持っている層への提供コンテンツ。
SNS投稿時には、共感フレーズを添えると反応率が高まります。
🎧「この設定、意外と見落としがちなんです…!」
そんな小さな工夫をまとめました👇
中堅記事は、“親しみ”をベースにした投稿トーンで、フォロワーとの関係を強化しましょう。
🟨 H3-3:低PV記事(〜100)=内部リンクで育成
低PV記事は、SNS上では主役にしづらいものの、育成と循環のカギになります。
直接投稿するよりも、花形・中堅記事に内部リンクとして組み込み、自然に流入させる戦略が効果的です。
- 投稿比率の目安:全体の10%以下(単独投稿は控えめに)
- 目的:検索で拾われにくいテーマを、SNS経由で再露出
たとえば👇
【人気記事】ダイソーイヤホンG273-3とG273-4を比較!
詳細レビューはこちら👉 https://earbuds.aspsv.com/2025y-daiso-comp4112/
(※ペアリングの細かい手順も別記事で紹介しています)
👉 https://earbuds.aspsv.com/daiso-wireless-earphones-manual-detailed-guide/
このように“付け足しリンク”として活用すれば、
低PV記事を直接宣伝せずに読んでもらう導線を作れます。
さらに、リライトや再投稿を続けながら、徐々にSNS単体での反応をテストするのも効果的です。
小さな成功を積み重ねることで、低PV記事から“次の中堅”が生まれていきます。
🟩 H2-6:実際に反応が取れるX投稿のコツ【テンプレ付き】
- H3-1:1ツイート=1テーマで完結させる
- H3-2:URL前に“共感フレーズ”を置く
- H3-3:ハッシュタグは2〜3個まで
- H3-4:【実例】PV上位記事/低PV記事の投稿文比較
🧩「#ブログ初心者」「#X運用」「#ブロガー仲間と繋がりたい」などのタグ活用も触れると拡散効果を解説できます。
🟩 H2-6:実際に反応が取れるX投稿のコツ【テンプレ付き】
SNS投稿で最も重要なのは、「どう書くか」です。
同じ記事URLでも、投稿文の作り方ひとつで反応率(クリック率・いいね率)が大きく変わります。
特にXでは、1ツイートごとの完成度=表示回数を左右します。
ここでは、反応が取れる投稿を作るための4つのポイントと、実際に使えるテンプレート例を紹介します。
🟨 H3-1:1ツイート=1テーマで完結させる
投稿を作るときは、1投稿につき1テーマに絞りましょう。
複数の記事URLを一気に載せたり、複数の要点を詰め込みすぎると、読者の注意が分散してしまいます。
悪い例:
【ダイソーイヤホンおすすめ5選】と【TWS005レビュー】を公開しました🎧
コスパ最高です!👇
https://earbuds.aspsv.com/2025y-daiso-comp4112/
https://earbuds.aspsv.com/daiso-tws005-review/
良い例:
🎧【ダイソーイヤホン比較】
1000円でこの音質?って思うレベル。
初心者でも失敗しない選び方はこちら👇
https://earbuds.aspsv.com/2025y-daiso-comp4112/
1テーマ1投稿にすると、「クリック→サイト閲覧」までの流れがスムーズになり、CTRが上がります。
🟨 H3-2:URL前に“共感フレーズ”を置く
Xの投稿では、**URLの前に「読者の感情に触れるひと言」**を入れると反応が格段に高まります。
SNSでは情報よりも“気持ち”が先に届くため、感情トリガーを上手に使いましょう。
例文テンプレート:
| タイプ | 共感フレーズ例 |
|---|---|
| 疑問系 | 「これ、知らないと損するレベル…」 「なぜか音が悪いと思ったら、原因はここにありました」 |
| 共感系 | 「同じ悩みを抱えてる人、意外と多いはず」 「これ、自分も最初つまずきました」 |
| 体験系 | 「実際に使ってみてわかったこと👇」 「正直ここまで変わるとは思わなかった…!」 |
例:
「これ、知らないと損するレベル…」
ダイソーの1000円イヤホン、実はここがすごい👇
https://earbuds.aspsv.com/2025y-daiso-comp4112/
共感フレーズ→タイトル要約→URLの流れにすると、感情→行動の流れが自然に生まれます。
🟨 H3-3:ハッシュタグは2〜3個まで
ハッシュタグは多すぎると読みづらく、CTRが下がります。
最適なのは2〜3個以内。ジャンルと読者層の両方を意識して設定しましょう。
おすすめタグ構成:
| 用途 | 例 |
|---|---|
| ジャンルタグ | #イヤホン #ワイヤレスイヤホン #ガジェット |
| 読者層タグ | #ブログ初心者 #音を楽しむ #暮らしを便利に |
| トレンドタグ | #ダイソー #コスパ最強 #新商品レビュー |
例:
🎧【LDAC対応スマホまとめ】
ハイレゾで聴きたい人は要チェック👇
https://earbuds.aspsv.com/ldac-for-smaho-list217/
#LDAC #高音質イヤホン #音を楽しむ
タグは投稿の検索導線になるため、毎回3〜5種類の候補をリスト化しておくと効率的です。
🟨 H3-4:【実例】PV上位記事/低PV記事の投稿文比較
最後に、反応が取れる投稿パターンを実例で比較してみましょう。
🔸 PV上位記事(拡散重視)
【2025年最新版】
ダイソーのワイヤレスイヤホンおすすめ5選🎧
コスパ最強×初心者でも失敗しないモデルまとめ👇
https://earbuds.aspsv.com/2025y-daiso-comp4112/
#ダイソーイヤホン #コスパ最強 #音を楽しむ
→ 強いタイトル+絵文字+具体性。リツイート・保存されやすい。
🔸 低PV記事(育成重視)
「ペアリングができない…」そんな時はこれ👇
ダイソーイヤホン説明書を写真付きで解説📖
https://earbuds.aspsv.com/daiso-wireless-earphones-manual-detailed-guide/
#イヤホン初心者 #ダイソー #音を楽しむ
→ 共感+課題解決フレーズを前面に出し、クリック率を高める。
このように、上位記事は“拡散向け”、低PV記事は“共感・解決向け”にトーンを変えるのがポイントです。
SNS投稿は「一律テンプレ」ではなく、記事の目的に合わせてチューニングすることで効果が倍増します。
🟩 H2-7:まとめ|SNS発信は「伸びている記事」から“戦略的に拡げる”
- H3-1:SNSはバズより「積み上げ型」の導線設計が重要
- H3-2:PVが少ない記事は“内部導線と再発信”で再生できる
- H3-3:今日からできる!SNS運用チェックリスト
📋最後に「次にやることリスト(例:①PV分布を出す→②主力記事を選ぶ→③X投稿文を作る)」を3ステップで提示。
🟩 H2-7:まとめ|SNS発信は「伸びている記事」から“戦略的に拡げる”
SNS運用は“バズを狙う一発勝負”ではなく、積み重ねによって成果を育てていく地道な設計作業です。
PVが伸びている記事を軸に、そこから関連コンテンツを丁寧に拡げていくことで、
サイト全体のアクセスと信頼が確実に積み上がっていきます。
SNSは「入口」ではなく「循環装置」。
ブログを資産化したいなら、この視点を持つことが最も重要です。
🟨 H3-1:SNSはバズより「積み上げ型」の導線設計が重要
Xでは、一度バズっても数日で流れてしまいます。
短期的な反応よりも、安定的にクリックされる投稿を積み上げる仕組みが結果的に長く効きます。
そのために必要なのは、以下の3ステップです。
- 反応が取れる主力記事(花形)を繰り返し投稿
- 関連する中堅記事を内部リンクで紹介
- 低PV記事を人気記事経由で自然に露出
このサイクルを続けることで、SNSが“PVを生み出す装置”に変わります。
ブログ運営はマラソンです。瞬発力よりも、戦略的な「導線設計」で勝負しましょう。
🟨 H3-2:PVが少ない記事は“内部導線と再発信”で再生できる
PVが少ない記事でも、完全に埋もれる必要はありません。
内部リンク+SNSでの再発信を組み合わせれば、記事は何度でも蘇ります。
- 人気記事に「関連記事」として内部リンクを追加
- タイトルや冒頭をリライトして再投稿
- 同ジャンルの記事を束ねてシリーズ投稿
このような“再設計”を加えるだけで、検索順位が動き出すケースも多く見られます。
実際、耳スタでも「クリック数50→300」「CTR0.3%→1.5%」など、
リライト+再投稿の連動で明確に改善した記事が複数あります。
SNSを活用することで、時間の経った記事をもう一度息づかせることができるのです。
🟨 H3-3:今日からできる!SNS運用チェックリスト
最後に、今日からすぐ実践できるSNS運用チェックリストをまとめます。
印刷してPC横に貼っておくレベルで使えます👇
✅ 投稿設計
- 投稿テーマは「1ツイート=1記事」
- URLの前に“共感フレーズ”を入れる
- ハッシュタグは2〜3個まで
✅ 記事選定
- PV上位記事を定期的に投稿(週3〜4回)
- 中堅記事はファン向けに共感コメントを添えて出す
- 低PV記事は人気記事経由でリンク紹介
✅ 改善・分析
- GA4でSNS流入のPVを確認
- CTRが低い投稿はタイトルと一言目を修正
- 反応率の高い時間帯を把握して再投稿
SNSは“テクニック”ではなく、“継続設計”です。
小さな改善の積み重ねが、半年後には確実にアクセスの山を作ります。
📈 まとめ
ブログ運営においてSNSはもはや補助ではなく、「PVを増やす第二の主戦場」。
伸びている記事を軸にしながら、関連ページへ導線を伸ばし、低PV記事を再生していく。
この「積み上げ型SNS戦略」こそ、2025年以降のブロガーに求められる新しい発信の形です。


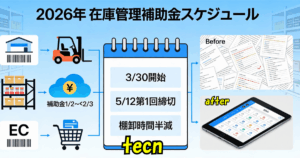
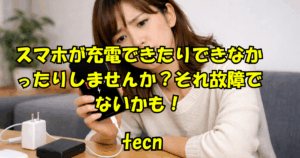




コメント