在庫コストを30%削減する方法|中小企業がすぐできる見直しポイント KL20
在庫が合わない、棚卸が終わらない──。
そんな「人手頼みの在庫管理」を根本から変える方法を解説しています。
在庫を仕組みで回すための“第一歩”として、こちらの記事もぜひご覧ください。
機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。
アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。
手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)

「在庫が多いのに利益が出ない」「倉庫が常にいっぱいでスペースが足りない」——その原因は、在庫コストにあります。
商品を保管するだけでも倉庫費用や人件費がかかり、過剰在庫が続くとキャッシュフローを圧迫します。
この記事では、在庫コストの内訳(保管・管理・廃棄など)を整理し、中小企業でもすぐ取り組める削減方法を具体的に紹介します。ITツールを活用して“無駄な在庫を持たない仕組み”をつくり、経営改善へつなげましょう。
H2-1|なぜ中小企業では在庫コストが膨らむのか?
在庫は「売上を支えるために必要な資産」である一方、
管理を誤ると“利益を圧迫するコスト”にもなる要素です。
特に中小企業では、システム化や分析体制が整っていないため、
「なぜこんなに在庫が増えたのか」が分からないまま、倉庫を圧迫してしまうケースが少なくありません。
ここでは、多くの中小企業に共通する“在庫コストが膨らむ3つの原因”を整理します。
H3|発注が「勘と経験」に頼っており、在庫が積み上がる
多くの企業では、発注数量の判断が担当者の“経験”や“肌感覚”に依存しています。
「この商品は売れている気がする」「念のため多めに仕入れておこう」といった判断が積み重なり、
実際の販売データとは乖離した在庫量になってしまうのです。
その結果:
- 売れ残り品の保管スペースが増える
- 棚卸や在庫確認にかかる時間が膨張
- キャッシュフローが悪化
つまり、“感覚発注”は一見安全に見えて、実は在庫コストを最も押し上げる要因です。
💡 対策の第一歩は「発注履歴を見える化」すること。
月次・週次で販売データと照らし合わせるだけでも、余剰発注を抑えられます。
H3|倉庫内で“死に筋”と“売れ筋”の区別が曖昧
倉庫の棚を見渡すと、**「売れる商品」と「動かない商品」**が同じように並んでいませんか?
この“分類できていない状態”こそが、在庫コストを増やす原因です。
- 売れ筋商品が奥に配置されてピッキング効率が低下
- 死に筋商品が棚を占有して保管スペースを圧迫
- 補充すべき商品を見落として欠品が発生
結果として、倉庫スペース・作業時間・機会損失のすべてが膨張します。
💬 対策としては、「販売頻度」「在庫回転率」「粗利率」などの軸で
A(主力)・B(通常)・C(低頻度)ランクに分類するだけでも、
倉庫の効率とコスト削減効果が一気に高まります。
H3|在庫評価・保管コストを「見える化」できていない
在庫コストが高止まりしている企業では、
**“在庫をコストとして認識していない”**ケースが多く見られます。
たとえば:
- 倉庫家賃・人件費を在庫保管コストに含めていない
- 棚卸のたびに「誤差分」を仕方ないと放置している
- 不良在庫を処分せず、帳簿上に残したまま
このように、在庫を「経費の一部」として扱わないまま管理していると、
どこでコストが発生しているのかが見えず、削減策を打ちにくくなります。
💡 まずは、以下のような指標を定期的に確認しましょう:
- 在庫回転率
- 在庫金額/売上比率
- 保管費(家賃・人件費)の在庫1個あたりコスト
データを“数値で見える化”することで、
「どこにムダがあるのか」が明確になり、改善の優先順位を付けられます。
🔍 小まとめ
| 原因 | 状況 | 結果 |
|---|---|---|
| 勘と経験での発注 | 実需を上回る仕入れ | 余剰在庫・キャッシュ圧迫 |
| 売れ筋と死に筋が混在 | 棚割り非効率 | 保管・作業コスト上昇 |
| コストの見える化不足 | 改善ポイントが不明 | 無駄な在庫を放置 |
在庫コストの膨張は、「仕入れすぎ」よりも「仕組みが見えていない」ことが本質的な原因です。
次章では、在庫コストの構成要素を分解し、どこを削るべきかを具体的に見ていきましょう。
H2-2|在庫コストを構成する3つの要素を理解する
在庫コストは、単に「商品を保管するための費用」ではありません。
その内訳を分解していくと、見えないコストが複数の段階で発生していることがわかります。
ここで重要なのは、
「減らすべき在庫コスト」と「減らしてはいけない在庫」を分けて考えること。
極端な在庫削減は欠品を招き、売上や信用を失うリスクもあります。
“最小化”ではなく、“最適化”を目指すのが中小企業における正しい在庫コスト改善の方向です。
H3|保管コスト(倉庫・棚・人件費)
在庫コストの中でも最も分かりやすく、しかも大きな割合を占めるのが「保管コスト」です。
主な構成要素:
- 倉庫・保管スペースの家賃や維持費
- 棚・設備・照明などの固定費
- 在庫管理や棚卸にかかる人件費
保管コストは、在庫量が多いほど雪だるま式に増えます。
特に中小企業では、倉庫スペースの拡張=コスト上昇という構図が多く見られます。
💡 まず見直すべきは「使っていない在庫がどれだけ場所を取っているか」。
売れない在庫を減らせば、新しい倉庫を借りずに済むケースもあります。
減らすべきコスト:スペース・保管物・人件費の“ムダ”
残すべき在庫:売れ筋・短期回転が明確な在庫
H3|調達・発注コスト(仕入頻度・ロット・発注作業)
在庫は「仕入れた瞬間」に発生します。
この仕入・発注プロセスそのものも、実は大きなコストを生んでいます。
主なコスト要素:
- 発注業務にかかる人件費(手入力・メール処理など)
- 発注ロットが大きすぎることによる余剰在庫
- 小ロットすぎて仕入単価が上がるケース
- 発注漏れや重複発注による在庫の混乱
ここでのポイントは、
「安く仕入れたのに在庫が積み上がってしまう」ことが最も高いコストになるという点です。
💬 “まとめ買い割引”は短期的には得でも、長期的にはキャッシュを圧迫するリスク。
販売データに基づく「適正在庫・適正発注」が、結果的にコストを下げます。
減らすべきコスト:作業負荷・ロット過多による余剰仕入れ
残すべき在庫:発注リードタイムを考慮した“必要最小限”の安全在庫
H3|欠品コスト(販売機会損失・信用低下)
在庫を減らすことばかりに集中すると、次に問題になるのが「欠品」です。
欠品は、単に“売れなかった”という損失だけでなく、取引先・顧客の信頼を損なうリスクも伴います。
代表的な欠品コスト:
- 販売機会損失(「在庫がないのでキャンセル」)
- 顧客満足度の低下(リピート率の減少)
- 取引先からの信用低下(納期遵守率の悪化)
とくにBtoB取引では、「一度の欠品で取引が止まる」ことも珍しくありません。
💡 欠品コストは“見えにくい”だけで、実際には売上・ブランド・信用の3つを同時に失う重大な損失です。
減らしてはいけない在庫:常に一定の販売実績がある定番・消耗品
見直すべき在庫:販売サイクルが遅く、回転率が低い商品群
🔍 小まとめ:コスト削減ではなく「在庫の最適化」を
| コスト種別 | 減らすべき要素 | 残すべき要素 |
|---|---|---|
| 保管コスト | 不動在庫・使われないスペース | 売れ筋商品の保管エリア |
| 調達コスト | 大ロット発注・発注ミス | 安定供給のための小ロット発注 |
| 欠品コスト | 欠品リスクの放置 | 安全在庫・リードタイム考慮 |
在庫コストは「全部減らす」ではなく、必要な在庫を残してムダをなくす“調整型改善”が正解です。
次章では、実際に30%削減を実現した具体的な見直しポイントを解説していきます。
H2-3|30%削減を実現する5つの見直しポイント
在庫コストを削減するうえで大切なのは、
大掛かりなシステム導入よりも、“今ある仕組みの中で見直す”こと。
ここでは、中小企業でも今日から取り組める5つの見直しポイントを紹介します。
どれも単独で実施しても効果があり、組み合わせることで在庫コストを30%以上削減することが可能です。
H3|① 売れ筋20%商品の在庫回転を優先管理する
在庫の中には、「売上の大半を支える少数商品」が存在します。
これは**“パレートの法則(80:20の法則)”**として知られ、
多くの現場では上位20%の商品が売上の80%を生み出しています。
したがって、在庫削減の第一歩は「すべてを均等に管理する」のではなく、
売れ筋20%を重点管理することです。
実践例:
- 販売履歴から上位20%の商品を抽出
- “売れ筋リスト”を常時チェックして発注・補充を優先
- 倉庫内ではホットゾーン(出荷頻度の高い棚)に配置
これにより、回転率の高い商品を切らさず、低回転在庫を自然に減らす仕組みが生まれます。
H3|② 発注ロットとリードタイムを短縮し、“適正在庫”化する
多くの企業では、「仕入れコストを下げるためにまとめ買い」する傾向があります。
しかし、仕入単価が下がっても在庫が増えれば、保管・管理コストが上昇して本末転倒です。
重要なのは、発注ロットとリードタイムのバランスを最適化すること。
実践例:
- 仕入先と交渉して発注ロットを半減(例:100個→50個単位)
- 発注から納品までのリードタイムを短縮し、在庫を持たない期間を短くする
- 月1回発注から週1回発注へ分割し、在庫ピークを抑制
これにより、キャッシュフローを健全化しながら在庫を圧縮できます。
H3|③ 棚卸頻度を上げて「データと実在庫」のズレをなくす
在庫コストを削減するには、まず「正確な在庫数」を把握することが前提です。
データ上の在庫と実際の在庫がずれていると、
余分な発注・誤出荷・欠品といったトラブルが発生し、結果的にコストが膨らみます。
実践例:
- 年1回だった棚卸を、月次・週次単位に小分けして実施
- 売れ筋商品だけ“重点棚卸”を行う仕組みを導入
- バーコード・スマホ入力でリアルタイム更新
💡 「こまめに数える」ことが、最も安くできる在庫精度の改善策です。
在庫データの精度が上がることで、ムダな発注が減り、
“見えない在庫コスト”が自然に削減されます。
H3|④ 長期滞留品・不良在庫をリスト化して処分・転用する
「売れない在庫」を抱えたまま放置すると、
スペース・管理工数・資金繰りのすべてを圧迫します。
まずは長期間動いていない在庫を**“可視化”**することから始めましょう。
実践例:
- 最終出荷日から6か月以上動いていない商品を一覧化
- 販促・値引きキャンペーンで在庫を消化
- 部品・原材料は他商品に転用
- 在庫管理システムに「滞留在庫アラート」を設定
📊 1年動かない在庫を1割減らすだけでも、倉庫コストは大幅に改善します。
H3|⑤ 在庫・販売・仕入データを連携させ、リアルタイム更新を実現
在庫管理の“見直しの最終段階”は、データ連携による自動更新です。
受注・販売・仕入・在庫がバラバラに管理されていると、
どんなに努力しても「ズレ」と「ムダ」はなくなりません。
実践例:
- 販売システムと在庫管理システムをAPIで連携
- 入出庫時にリアルタイム更新を自動反映
- 売上データを分析して、補充・発注を自動化
これにより、
人の判断では追いつかない在庫変動を、システムが瞬時に調整します。
結果として、余剰在庫・欠品・作業ミスが同時に減少。
💬 データ連携による「リアルタイム在庫管理」は、
在庫コスト削減だけでなく、経営判断のスピードアップにもつながります。
🔍 小まとめ
| 対策 | 効果 |
|---|---|
| 売れ筋20%管理 | 回転率向上・欠品防止 |
| 発注ロット最適化 | 仕入・保管コスト削減 |
| 棚卸頻度UP | 在庫精度向上・誤発注防止 |
| 不良在庫処分 | 保管スペース削減・資金回収 |
| データ連携 | リアルタイム化・人件費削減 |
これら5つの見直しは、設備投資ゼロでも実施可能な施策です。
小さな改善の積み重ねが、確実に“30%のコスト削減”を実現します。
H2-4|在庫管理システムを使えば「感覚管理」から「数値管理」へ
在庫コストを30%削減するうえで欠かせないのが、
“感覚で動く在庫管理”から“データで判断する管理”への転換です。
エクセルや紙ベースでの管理でも一見「把握できている」ように見えますが、
実際には、
- 入力ミス
- 更新漏れ
- 棚卸タイミングの遅れ
などにより、在庫データと実在庫の差がどんどん広がっていきます。
在庫管理システムを導入すれば、在庫状況・回転率・金額をリアルタイムで把握でき、
**“数字が語る在庫管理”**を実現できます。
H3|エクセル管理の限界とミスのコスト
中小企業では今も、エクセルで在庫を管理している現場が少なくありません。
しかし、エクセルは手軽である反面、ヒューマンエラーの温床になりやすいのが現実です。
よくある問題点:
- 入出庫を都度手入力 → 更新漏れ・重複登録が発生
- 複数人で編集 → ファイルのバージョンが分からなくなる
- 商品コード・品番の打ち間違いで誤出荷
- 集計や分析に時間がかかり、判断が遅れる
こうした“小さなミス”が積み重なると、
在庫差異・誤発注・欠品といった損失が年間で数十万円〜数百万円単位になることもあります。
💡 在庫コストを下げたいなら、まず「手作業コストを減らすこと」から。
データ入力の自動化・連携こそが、最も確実な改善です。
H3|在庫回転率・在庫金額を自動可視化して意思決定を早くする
在庫管理システムの大きな強みは、
「数字が自動で見える化される」ことです。
たとえば、以下のような指標がボタン1つで確認できます。
- 在庫回転率(=販売スピードの指標)
- 在庫金額(=在庫にいくら資金が眠っているか)
- 滞留在庫率(=一定期間動いていない商品の割合)
これらをリアルタイムで把握できれば、
「どの商品を仕入れるべきか」「どれを処分すべきか」が即座に判断できます。
実践例:
- 在庫回転率が低い商品を抽出 → 値下げ・販促で早期回収
- 高回転商品を分析 → 仕入頻度を増やし欠品を防止
- 定期レポートで“現場任せ”から“経営判断”へシフト
📊 データを“見える化”するだけで、在庫削減の8割は実現できると言われています。
H3|売れ筋・死に筋をAI・分析で分類し、発注精度を高める
近年の在庫管理システムは、単なる「記録ツール」ではなく、
**AIや分析機能によって“判断を支援するツール”**へと進化しています。
AI分析を活用すれば、
- 販売履歴・季節変動・取引先別データから「売れ筋」を自動抽出
- 動きのない商品を「死に筋」としてアラート表示
- 需要予測を基に「次の発注タイミング」を自動算出
といった仕組みが可能です。
現場の変化イメージ:
これまで担当者が「そろそろ仕入れておこう」と勘で判断していた発注が、
システムによって**“必要な時に、必要な分だけ”**発注されるようになる。
結果として、
- 過剰発注の削減
- 欠品リスクの回避
- 資金繰りの改善
が同時に実現します。
💬 感覚ではなくデータで判断することで、
在庫は“守りの資産”から“攻めの経営データ”に変わります。
🔍 小まとめ
| 管理方法 | 特徴 | 主な課題 | システム導入後の変化 |
|---|---|---|---|
| エクセル管理 | 手軽だが属人的 | ミス・更新漏れ・遅延 | データ自動更新・リアルタイム反映 |
| 感覚発注 | 担当者依存 | 余剰在庫・欠品 | AI分析で精度向上 |
| 手動集計 | 時間がかかる | 判断が遅れる | 指標自動算出・迅速な意思決定 |
在庫管理システムの導入は、単なる業務効率化ではなく、
**“在庫を経営データとして活かす第一歩”**です。
H2-5|導入事例|在庫コストを30%削減した中小企業の取り組み
在庫コストの削減は、「単なる節約」ではなく、
経営の健全化・資金繰りの安定・現場の生産性向上を同時に実現する取り組みです。
ここでは、実際に在庫管理システムやデータ連携の仕組みを導入し、
30%以上のコスト削減に成功した中小企業の3つの事例を紹介します。
H3|製造業A社:余剰部品を50%削減し、キャッシュフローを改善
A社は、自動車部品の製造・組立を行う中小製造業。
これまで、発注担当者が生産計画と在庫をエクセルで別々に管理しており、
「部品の在庫があるのに、また仕入れてしまう」という重複発注が頻発していました。
課題:
- 部品点数が多く、在庫一覧が追いつかない
- 生産ライン停止を恐れて“安全在庫”を過剰に保有
- 資金繰りが圧迫され、月末仕入の支払いが重荷に
施策:
在庫管理システムを導入し、生産計画・仕入・在庫データを一元化。
リアルタイムで部品残数・発注履歴を共有できる仕組みを構築。
効果:
- 余剰部品を約50%削減
- 倉庫の棚卸時間が半分に短縮
- キャッシュフローが安定し、仕入先への支払いサイクルもスムーズに
💡 “ラインを止めないための在庫”から“データでコントロールする在庫”へ。
A社では、部品在庫の適正化が利益改善に直結しました。
H3|EC業B社:在庫の「見える化」で倉庫スペースを3割縮小
B社は、ネットショップを複数運営するEC企業。
シーズンごとに商品の入れ替えが多く、在庫の入出荷が複雑化していました。
「どの商品が、どの倉庫に、どれだけあるのか」が曖昧で、
過剰在庫・欠品・返品が同時に発生していたのです。
課題:
- 倉庫が商品であふれ、ピッキング効率が低下
- 販売履歴と在庫の照合が手作業
- シーズンオフ商品の滞留による倉庫コスト増加
施策:
クラウド型の在庫管理システムを導入し、
販売データ・出荷履歴・在庫状況をリアルタイムで可視化。
特に「売れ筋商品を優先配置」「動かない在庫を自動抽出」の機能を活用。
効果:
- 倉庫スペースを3割縮小(外部倉庫の契約を解約)
- ピッキング効率20%向上
- 在庫評価額を常時把握できるようになり、経営判断が迅速化
💬 “感覚で補充”から“データで在庫を動かす”仕組みが定着。
B社では、システム導入後わずか3か月で倉庫コストの圧縮を実現しました。
H3|卸売業C社:在庫回転率1.8倍、発注担当者の工数を半減
C社は、日用品・生活雑貨を取り扱う地域卸売業。
取扱点数が1,500以上あり、担当者ごとの発注判断がバラバラ。
同じ商品を複数ルートで仕入れるなど、在庫が分散していました。
課題:
- 担当者による「個人管理」状態で在庫統制が不十分
- 発注に1日2〜3時間を要し、他業務に支障
- 売れ筋と滞留品の把握ができない
施策:
在庫管理システムで取引先別・商品別の販売履歴を分析。
AIによる需要予測機能を活用し、発注ロットとタイミングを自動化。
効果:
- 在庫回転率が1.8倍に向上
- 発注担当者の工数を半減(1日→30分)
- 欠品率が2.3%→0.9%に改善
💡 「データで仕入れる」文化を定着させることで、
在庫は減っても、販売機会は増える。
C社では、人手不足対策としても大きな成果を上げています。
🔍 小まとめ
| 企業業種 | 主な課題 | 導入効果 |
|---|---|---|
| 製造業A社 | 重複発注・余剰部品 | 余剰在庫50%削減・資金繰り改善 |
| EC業B社 | 倉庫過密・在庫不明瞭 | 倉庫コスト3割削減・出荷効率20%UP |
| 卸売業C社 | 担当者依存・発注遅延 | 在庫回転率1.8倍・工数半減 |
3社に共通しているのは、
**「在庫を減らす」ではなく「在庫を動かす仕組みを作った」という点です。
在庫管理システムは単なるツールではなく、
中小企業にとって“利益を生み出すデータ基盤”**になりつつあります。
H2-6|まとめ|在庫コスト削減は“減らす”ではなく“整える”
在庫コストの削減は、「とにかく在庫を減らす」ことではありません。
むしろ大切なのは、**必要な在庫を確保しつつ、ムダを減らす“整える発想”**です。
在庫は企業の血液のようなもので、
減らしすぎれば「欠品」や「機会損失」という新たなリスクを招きます。
逆に持ちすぎれば、保管費・人件費・資金繰りが圧迫されます。
つまり、目指すべきは「在庫量の最小化」ではなく、
**“在庫バランスの最適化”**です。
H3|在庫量ではなく在庫バランスを最適化することが目的
在庫コスト削減の本質は、
「どの商品を、どれだけ、どこに置くか」を最適化することにあります。
たとえば、売れ筋商品の在庫が足りず、
動かない在庫ばかりが棚を占領している――この状態こそがコストの正体です。
理想的な状態とは:
- 売れる商品が常に適正量だけ確保されている
- 滞留在庫が減り、キャッシュが循環している
- 倉庫スペース・作業動線がスリム化されている
このバランスを保つためには、
**「販売データに基づく在庫判断」と「リアルタイム更新」**の仕組みが不可欠です。
💡 在庫コスト削減=“経営の筋肉化”
不要な脂肪(ムダ在庫)を落とし、必要なエネルギー(回転在庫)を維持することが理想です。
H3|小さな見直しを継続すれば、30%削減は現実的に達成できる
在庫コスト削減は、一度の改革では終わりません。
**小さな改善を積み重ねる「継続型プロジェクト」**として取り組むことが成功のカギです。
すぐに始められる行動例:
- 月1回、「売れない在庫リスト」を更新して現場で確認
- 棚卸結果を経営会議に共有し、次月の発注に反映
- 売れ筋20%商品を常に監視し、欠品ゼロを維持
これらの積み重ねが、結果的に30%以上のコスト削減を生みます。
そしてその効果は、利益率の改善・現金余力の増加・業務の安定化といった
経営全体の好循環へとつながります。
💬 「大きく変える」より、「小さく始めて続ける」。
それが中小企業にとって、最も現実的で確実な改善アプローチです。
🔍 総括
| 見直しの方向性 | ゴール |
|---|---|
| 減らす → 整える | 適正在庫でキャッシュを動かす |
| 感覚管理 → 数値管理 | データで判断できる経営へ |
| 単発改善 → 継続改善 | 恒常的なコスト最適化 |
在庫コスト削減は、「在庫を敵にしない」取り組みです。
“持つ”ことを否定するのではなく、“動かす”仕組みを整えることで、
利益と安定を両立した在庫経営が実現します。
機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。
アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。
手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)
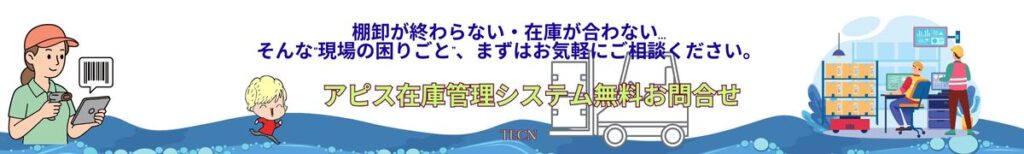

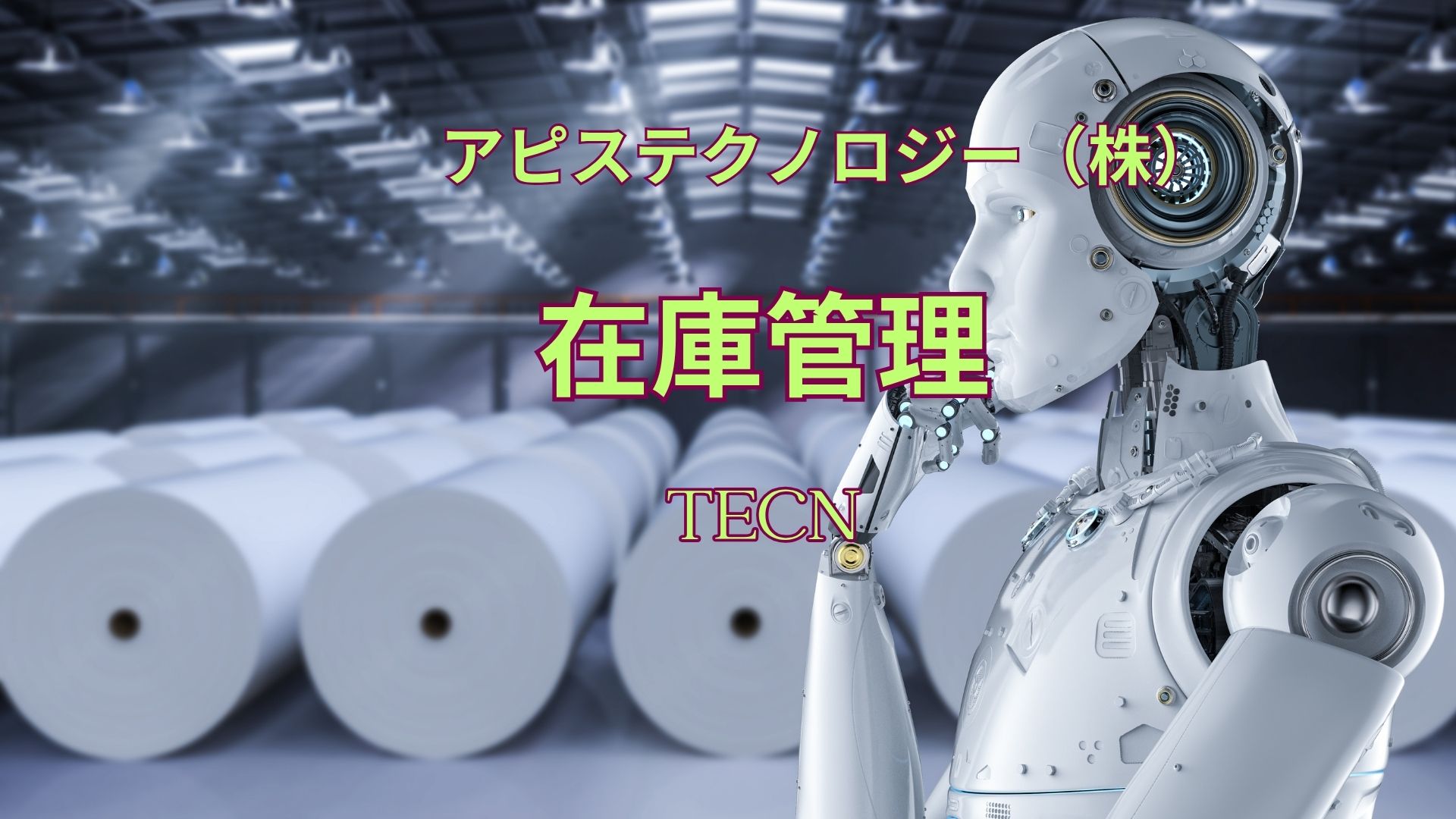
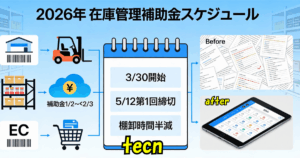
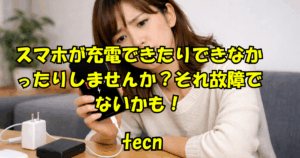




コメント