在庫ズレを防ぐ5つの対策|理論在庫と実在庫のズレをなくす管理方法 クラスター3
在庫数が「帳簿では10個なのに、倉庫には7個しかない」。
棚卸のたびにこんなズレが見つかり、原因が分からないまま“場当たり対応”を続けていませんか?
在庫ズレは、担当者が悪いわけでも、棚卸が下手なわけでもありません。
日々の業務の中に潜む“小さなズレ”が積み重なることで発生する、構造的な問題 です。
しかもこのズレは、売上・原価・利益・納期…あらゆる経営数字に影響し、
放置すると「欠品」「過剰在庫」「資金ロス」「信用低下」という経営リスクに直結します。
本記事では、
- なぜ在庫ズレが起きるのか(理論在庫 vs 実在庫)
- 日常業務に潜む“ズレの芽”
- ズレがもたらす経営への影響
- 現場でできる在庫ズレを防ぐ5つの対策
- エクセル管理ではズレが防げない理由
- クラウド在庫管理で根本解決する方法
までを 中小企業の現場向けに分かりやすく解説 します。
在庫ズレは「人のミス」ではなく、「仕組みが古い」サインです。
今日からできる改善策を一緒に見ていきましょう。
【5秒でわかる】在庫改善チェック
- 入荷/出荷/在庫が一致しない
- エクセル更新が遅れる・作業が属人化している
- SKU・棚番・ロケーションがバラバラ
- 欠品/ダブリ在庫が発生する
- 受注が急増すると一気に破綻する
→ 1つでも当てはまれば “改善の伸びしろ” があります。 このサイトでは在庫管理の基礎から実務改善まで、テーマ別にわかりやすく整理しています。 ぜひ関連ページもあわせてご覧ください。
在庫が合わない、棚卸が終わらない──。
そんな「人手頼みの在庫管理」を根本から変える方法を解説しています。
在庫を仕組みで回すための“第一歩”として、こちらの記事もぜひご覧ください。
在庫管理がうまくいかないのは「人」ではなく「仕組み」|中小企業が3日で変わるクラウド導入の現場
機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。
アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。
手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)

H2-1|なぜ在庫ズレは起きるのか? ― 理論在庫と実在庫のギャップ
在庫ズレは、ほとんどの企業や倉庫で日常的に発生しています。
「棚卸のときだけ発覚する一時的なミス」ではなく、実際には**日々の業務の中で少しずつ蓄積される“情報と現物のズレ”**が原因です。
まずは、その仕組みを理解することが在庫精度を高める第一歩になります。
📘 在庫管理がうまくいかないのは「人」ではなく「仕組み」|中小企業が3日で変わるクラウド導入の現場
H3-1:理論在庫と実在庫の違いを正しく理解する
在庫には大きく分けて2種類あります。
- 理論在庫(帳簿在庫):
システムやエクセル上で管理されている数値。入庫・出庫・返品などの記録から算出される「計算上の在庫」です。 - 実在庫(現物在庫):
倉庫や店舗に実際に存在する“モノ”の数。棚卸を行うことで初めて確認できる数量です。
理論在庫と実在庫が一致している状態が理想ですが、現場では人の操作・登録のタイミング・連絡の抜け漏れなどが重なり、
この2つの数値がズレていきます。これが「在庫ズレ(在庫差異)」と呼ばれる現象です。
H3-2:在庫ズレが起きる主な原因5つ
現場ではさまざまな業務要因が在庫差異を生み出します。代表的なものを見てみましょう。
- 入出庫の登録漏れ・遅れ
→ 実際に出庫したのにシステム入力を後回しにしてしまう。特に「急ぎの出荷」「顧客対応中の抜け」などで発生しやすい。 - 返品・不良品処理の未登録
→ 不良品を倉庫に戻しても、システム上は“販売済み”のまま。結果として理論在庫と現物が合わなくなる。 - 棚卸時の入力ミス
→ 二重カウントや未入力、計測単位の混在など、人的要因で誤差が生じる。 - ロット・製番・賞味期限管理の混乱
→ 同じ品番でもロット違いを混同して出庫してしまうケース。特に食品・医薬・製造業で頻発。 - 例外処理(緊急出庫・サンプル提供・検品出し)の未記録
→ 「すぐ返すから」「後で登録する」で放置されるケース。最も多い在庫ズレの原因。
これらの一つひとつは小さな出来事でも、日々の積み重ねで数%単位のズレとなり、
棚卸や決算時に大きな差異として表面化します。
H3-3:ズレは棚卸時に発生するのではなく“日常業務で育つ”
多くの現場で誤解されがちなのが、「棚卸でズレが生じた」という認識です。
実際には、ズレは棚卸で“見つかる”だけで、“生まれている”のは毎日の作業現場です。
たとえば次のような流れが典型例です。
・返品処理を後日まとめて登録
・不良品を廃棄したがシステム上は販売可能状態のまま
・検品中の商品を“一時保留”にしたが、そのまま在庫反映を忘れた
こうした小さな“例外業務”が放置されることで、理論在庫と実在庫が徐々に乖離していきます。
つまり、在庫ズレは「人の怠慢」ではなく、「現場の情報フローが分断されている」ことが本質的な問題です。
💡 ポイントまとめ
- 在庫ズレは棚卸時の“ミス”ではなく、日常業務の“情報断絶”で生まれる
- 理論在庫=帳簿上の数値、実在庫=現物の数
- ズレをなくすには、リアルタイムでの入出庫登録と情報共有が不可欠
このように、在庫ズレは現場オペレーションの設計そのものに起因します。
次の章では、こうしたズレが経営数字にどのような悪影響を与えるのかを具体的に見ていきましょう。
関連記事|在庫ズレの“原因”を日常業務から直す
H2-2|在庫ズレが引き起こす3つの経営リスク
在庫ズレは単なる“数の誤差”ではありません。
放置すれば、売上・利益・信用の3つの側面で企業経営を揺るがすリスクに発展します。
特に中小企業では、人員や資金の余裕が限られているため、
在庫の不一致がそのまま「経営の歪み」に直結します。
ここでは、具体的にどのようなリスクが生じるのかを整理していきましょう。
H3-1:欠品・過剰在庫による販売機会と資金の損失
在庫ズレが生じると、まず問題になるのが販売機会の損失と資金繰りの悪化です。
たとえば、帳簿上では在庫が「残り10個」となっていても、
実際の倉庫にあるのは7個だった場合――
追加注文に対応できず、せっかくの受注を逃す可能性があります。
逆に、実在庫が多いのに帳簿上で「在庫ゼロ」となっていると、
不要な追加発注を行い、資金を寝かせてしまうことになります。
このような「欠品・過剰在庫の両極化」は、最終的に売上の機会損失とキャッシュフローの悪化という形で経営を圧迫します。
💬 ある卸売業では、在庫ズレ率3%が年間約400万円の在庫ロスにつながったという報告もあります。
小さな誤差でも、数量・単価・取引量が多いほど損失は加速度的に増大します。
H3-2:原価・利益計算のズレによる経営判断の誤り
在庫の数量が正しくなければ、原価計算や利益率も正しく算出できません。
製造業や小売業では、在庫の増減がそのまま「仕掛品・原材料・完成品」の評価に影響します。
帳簿上の在庫が実際より多いと、利益が多く見える「見かけの黒字」が発生。
逆に少ない場合は、本来の利益を過小評価してしまいます。
経営層がこの誤った数字をもとに仕入れ・販売計画を立てると、
「実態と違う在庫を前提にした誤った意思決定」が起こります。
結果的に、利益を生まない在庫を増やす、あるいは機会損失を拡大させるという悪循環に陥ります。
📊 正確な在庫は、単なる物流データではなく“経営判断の羅針盤”です。
その精度が下がれば、経営の舵取りも狂ってしまいます。
H3-3:取引先・社内・監査対応での信頼低下
在庫ズレは、社内だけでなく外部との信頼にも影響を及ぼします。
- 納期遅延:在庫があると思っていた商品が実際には不足しており、取引先への出荷が間に合わない
- 会計監査での指摘:在庫金額の整合性が取れず、再集計・修正対応が必要になる
- 社内トラブル:現場と経理・営業の間で「どちらがミスをしたのか」という責任追及が発生
これらは一時的なトラブルにとどまらず、**「在庫データ=信用情報」**という本質的な価値を損ないます。
特にBtoB取引では、納期や数量の正確さが信頼関係の基盤。
在庫ズレが常態化している企業は、長期的な取引先から敬遠されることもあります。
⚠️ “在庫が信用”という考え方を持つことが、
これからのデータ経営時代における企業競争力の基本です。
🔍 まとめ:在庫ズレのリスクは経営全体に波及する
| リスクの種類 | 主な影響 | 長期的な結果 |
|---|---|---|
| 欠品・過剰在庫 | 売上損失・資金ロス | キャッシュフロー悪化 |
| 原価ズレ | 利益計算誤差・誤った経営判断 | 在庫過多・赤字化リスク |
| 信用低下 | 取引停止・社内不信 | 組織全体のモラル低下 |
💡 在庫ズレは「経営数字のブレ」であり、「信用のブレ」でもあります。
数字の精度を高めることは、単なる効率化ではなく経営リスクの最小化そのものです。
H2-3|現場でできる!在庫ズレを防ぐ5つの実践対策
在庫ズレの原因が「日常業務の情報のズレ」である以上、
その対策も現場レベルでの仕組みづくりと習慣化が欠かせません。
ここでは、今日から実践できる「在庫ズレを防ぐ5つの具体策」を紹介します。
どれも特別なシステムを導入しなくても、現場の意識とルール整備で始められる内容です。
H3-1:入出庫を“リアルタイムで登録”する習慣化
最も基本であり、最も重要なのが入出庫の即時登録です。
たとえば「後でまとめて入力する」「出荷後に処理する」といった運用では、
担当者の記憶に頼る時間が生まれ、そこにズレが入り込みます。
✅ 原則ルール:
出庫 → 登録 → 出荷
入庫 → 検品 → 登録
この順序を徹底するだけで、在庫ズレの8割は防げるとも言われます。
モバイル端末やタブレットから登録できる仕組みを整えると、
作業中でも即入力でき、精度が飛躍的に向上します。
💡 ポイント:「作業と入力を分けない」ことが最も効果的なズレ防止策です。
H3-2:返品・不良品処理を“即時に”記録するルール化
返品や不良品は、在庫ズレの温床です。
現場では「一時的に保管」「後でまとめて廃棄」といったケースが多く、
システム上では「まだ在庫がある」と誤認されがちです。
返品や廃棄が発生した時点で、原因・数量・処理日時を即時登録することが大切です。
また、返品専用のステータス(例:「検品待ち」「廃棄予定」)を設けることで、
現物とデータの不整合を防げます。
💬 返品は「商品を戻す作業」ではなく「情報を更新する作業」として扱う意識を持ちましょう。
H3-3:バーコード・ハンディターミナルを活用する
バーコードスキャンによる入出庫登録は、手入力よりも圧倒的にミスを減らせます。
商品コードの打ち間違い、数量誤入力、ロット違いなどの人的ミスを防ぎ、
誰がいつ登録したかの履歴も残せます。
📱 小規模事業でも、バーコードリーダー付きの安価なハンディ端末やスマホアプリを導入すればOK。
Excel+バーコードスキャン連携など、低コストの仕組みも増えています。
ハンディ導入は“在庫データを人に依存させない”ための第一歩です。
H3-4:棚卸サイクルを短縮し、“ズレを早期発見”する
年1回や半年ごとの棚卸では、ズレが大きくなりすぎて原因が追えません。
理想は、**毎月または四半期ごとの循環棚卸(サイクルカウント)**です。
特定の商品群やロケーションごとに分けて棚卸を行えば、
作業負荷を分散しつつ、ズレを早期に発見できます。
💡 月1回・30分でもいいから、部分的に棚卸を行う仕組みを作ること。
「棚卸=決算業務」から「棚卸=日常メンテナンス」へ発想を転換しましょう。
H3-5:誰でも見える“在庫ダッシュボード”を導入する
在庫情報を「現場だけが見ている」状態では、
営業・購買・経理との間で認識ズレが生まれます。
リアルタイムで在庫数・出荷予定・入庫予定を共有できる在庫ダッシュボードを導入することで、
全員が同じ情報をもとに動けるようになります。
📊 特にクラウド型在庫管理システムでは、
スマホ・PCどちらからでもアクセスでき、
「倉庫に聞かなくても在庫がわかる」状態を実現できます。
💬 在庫情報の透明化は、ズレの防止だけでなく、社内連携の円滑化にもつながります。
🧾 5つの対策まとめ
- 入出庫はリアルタイム登録
- 返品・不良は即時記録
- バーコード運用でヒューマンエラー削減
- 棚卸サイクルを短縮し定期化
- 在庫を“全員で見る”ダッシュボードを活用
これら5つを徹底すれば、在庫ズレの多くは日常業務レベルで解消可能です。
次の章では、これらの対策を阻む「エクセル管理の限界」について掘り下げていきます。
💡
エクセル管理から脱出!在庫ズレを生まない仕組み化のメリット
🧾
棚卸ミスを防ぐための実践改善法を見る
H2-4|エクセル管理ではズレが防げない理由
在庫ズレの多くは、現場の運用ルールや情報共有の問題に起因しますが、
もう一つ見逃せない根本要因があります。
それは「エクセルというツールの構造的な限界」です。
中小企業や個人事業では、長年エクセルで在庫を管理してきたケースが多いですが、
在庫の精度を維持しようとするほど、手間とリスクが比例して増大していきます。
ここでは、なぜエクセルでは在庫ズレを完全に防げないのかを具体的に見ていきましょう。
H3-1:担当者依存と更新遅延 ― 「人が触る」ことがズレを生む
エクセル管理では、在庫更新のたびに手作業で数値を入力する必要があります。
そのため、担当者の判断・タイミング・スキルに依存しており、
入力忘れ・上書きミス・集計漏れが発生しやすくなります。
例:
- 出荷を終えてから入力を思い出す
- 関数やマクロの式が崩れて、在庫数が不一致
- 担当者が休みの日は更新が止まる
このように、人が操作するたびにズレのリスクが生まれるのがエクセルの構造的弱点です。
また、担当者の交代時に引き継ぎがうまくいかず、ファイル構造がブラックボックス化することも少なくありません。
⚠️ 「属人化」と「更新遅延」は、エクセル管理における最大の在庫精度リスクです。
H3-2:複数人・複数拠点では“整合性”が維持できない
在庫情報は、倉庫・店舗・事務所など複数の拠点で扱われます。
しかしエクセルでは、複数人が同時に正しいデータを扱うことが困難です。
典型的なケース:
- 同じファイルを複数人で同時編集 → 上書き・競合が発生
- メールでやり取り → 古いファイルを上書きして混乱
- Googleスプレッドシートにしても、データ量が増えると処理が重くなる
つまり、現場が増えるほど「誰のデータが最新なのか」が不明確になります。
これが、理論在庫と実在庫のズレを拡大させる温床となります。
💬 在庫は「1つの真実(Single Source of Truth)」で管理しなければ、精度を保てません。
そのためには、リアルタイム共有ができる仕組みが必須です。
H3-3:履歴・ロット・担当者情報を追跡できない
エクセルは「今の在庫数」を管理するには便利ですが、
「なぜその在庫数になったのか」を追跡するには不向きです。
たとえば、
- どの担当者が、いつ、どの出庫を登録したのか?
- 返品や不良品の在庫は、どのロットから発生したのか?
- 棚卸差異は、どの期間・どの商品で多かったのか?
こうした履歴管理は、手動で別シートを作るしかなく、現実的ではありません。
結果として、問題が発生したときに原因を特定できず、再発防止もできないという悪循環に陥ります。
⚙️ 履歴追跡ができない=“問題を改善できない仕組み”
これが、エクセル在庫管理の最大の限界です。
💡 まとめ:エクセルは“帳簿”には向いても“運用”には向かない
| 比較項目 | エクセル管理 | クラウド在庫管理システム |
|---|---|---|
| 入出庫更新 | 手動入力・更新遅れ | 自動反映・リアルタイム共有 |
| 拠点間共有 | メール・共有フォルダで分散 | 一元化(複数拠点でも整合性維持) |
| 履歴・ロット管理 | 手動管理・追跡困難 | 自動履歴・担当者記録 |
| 棚卸対応 | 都度入力・整合に時間 | 現場更新と自動差異計算 |
| 導入・運用コスト | 初期費用ゼロだが人的コスト大 | 月額コストありだが作業効率化大 |
💬 結論:
エクセルは「在庫を管理するツール」ではなく、「在庫を記録する表」に過ぎません。
現場がリアルタイムに動く今の時代、データを一元化し、履歴を自動で残す仕組みが不可欠です。
在庫が合わない、棚卸が終わらない──。
そんな「人手頼みの在庫管理」を根本から変える方法を解説しています。
在庫を仕組みで回すための“第一歩”として、こちらの記事もぜひご覧ください。
在庫管理がうまくいかないのは「人」ではなく「仕組み」|中小企業が3日で変わるクラウド導入の現場
機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。
アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。
手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)

💻 エクセル在庫管理から脱出!クラウド化でズレを防ぐ3つの効果
H2-5|システム化でズレを根本解消 ― クラウド在庫管理の導入効果
ここまで紹介してきたように、在庫ズレの原因は「人の操作」や「情報共有の遅れ」にあります。
つまり、根本的な解決には人の作業をシステムに置き換え、リアルタイムで情報を同期する仕組みが不可欠です。
その中核となるのが「クラウド在庫管理システム」。
近年では中小企業でも導入が進み、エクセル運用から脱却して在庫の“見える化”を実現する企業が増えています。
ここでは、クラウド化によって得られる3つの導入効果を整理します。
H3-1:リアルタイム更新で「在庫の今」が見える
クラウド在庫管理システムでは、入庫・出庫・返品などの操作が登録された瞬間に、
全ユーザーの画面に最新情報として反映されます。
📦 たとえば:
- 倉庫で入庫登録 → 営業が即座に在庫数を確認
- 出荷完了 → 経理が自動で在庫原価を更新
- 棚卸中の差異 → 管理者がリアルタイムでチェック
このように、現場・営業・経理が常に同じデータを共有できることで、
「今の在庫は正しいのか?」という不安を解消できます。
💬 在庫ズレを“防ぐ”から“発生させない”へ──。
情報の即時反映こそ、クラウド化の最大の強みです。
H3-2:履歴・ロット・担当者情報まで自動で追跡できる
在庫の数だけでなく、**「誰が・いつ・どのロットを扱ったか」**が自動で記録されます。
これにより、
- 棚卸差異が起きた時に担当者・日時を特定できる
- 不良品や返品のロット追跡が容易になる
- トレーサビリティ(追跡性)の確保で監査対応もスムーズ
特に製造業や食品業界のように「ロット管理」や「消費期限」が関わる業種では、
この履歴機能が品質保証とコンプライアンス対応の要になります。
⚙️ Excelでは“誰が入力したか”を追えませんが、クラウドなら履歴は自動保存。
「管理しなくても、管理されている」状態を作り出します。
H3-3:導入コストを抑えつつ運用効率を最大化できる
「システム導入は高い」と思われがちですが、
近年は月額1万円前後で使えるクラウド在庫管理システムも増えています。
初期費用がほとんどかからず、
ブラウザやスマホからアクセスできるため、特別な設備投資も不要です。
📈 導入効果の一例:
- 棚卸作業時間が50%削減
- 入出庫登録ミスが70%減少
- 欠品対応・問い合わせ対応の時間が1/3に短縮
つまり、導入コストよりも人的ミス削減・作業効率化による利益効果の方が大きいのが実情です。
💡 「高いから導入しない」ではなく、「導入しないことで失うコスト」を見直す視点が重要です。
💬 まとめ:在庫ズレを“仕組みで防ぐ”時代へ
| 比較項目 | 従来の運用 | クラウド在庫管理システム |
|---|---|---|
| 入出庫登録 | 手動入力・タイムラグ | 自動同期・即時反映 |
| 棚卸対応 | 手作業で修正 | 差異自動算出・履歴追跡 |
| 情報共有 | 各部署ごとに分断 | 全社でリアルタイム共有 |
| コスト構造 | 人件費・確認工数増大 | 月額制・定額で運用可能 |
🔍 ポイント:
在庫ズレをなくすには、人的努力よりも仕組みの最適化。
「正確な在庫を、誰もが見える形で共有できる環境」を整えることが、
これからの在庫管理のスタンダードです。
H2-6|まとめ ― 在庫ズレは“人の問題”ではなく“仕組みの問題”
在庫ズレは、どの企業にも起こり得る「日常業務の副作用」です。
しかし、その原因を「担当者のミス」や「現場の不注意」として片づけてしまうと、
何度改善しても同じ問題が繰り返されます。
本質的な解決策は、人の注意力ではなく、情報を正確に流す仕組みづくりにあります。
H3-1:在庫精度を支えるのは“正しいプロセス”と“見える化”
在庫の正確さを守るには、
- 入出庫をリアルタイムに登録する
- 返品・不良品をその場で記録する
- 全員が同じ在庫情報を共有する
といった、現場プロセスの標準化とデータの見える化が欠かせません。
これをシステム的に実現するのが、クラウド在庫管理システムです。
在庫数だけでなく、担当者・ロット・取引履歴まですべてが自動で追跡され、
「いつ・どこで・誰が」動かしたのかが明確になります。
これが、在庫ズレを防ぐ最大の武器です。
H3-2:“人が頑張る”から“仕組みで守る”へ
在庫管理を「人が頑張る業務」として続ける限り、ズレはゼロになりません。
必要なのは、“人が間違えてもズレが起きない仕組み”を整えることです。
⚙️ たとえば、
- 手入力ではなくスキャン登録
- 棚卸は手計算ではなく差異自動算出
- ファイル共有ではなくリアルタイム同期
こうした仕組みを導入することで、
「人が動いても在庫が狂わない」状態をつくることができます。
H3-3:在庫精度=経営の信頼性
在庫は、単なる“倉庫のデータ”ではなく、企業の経営基盤を支える数字です。
在庫がズレるということは、利益・原価・納期、すべての数字に誤差が生じるということ。
💬 在庫の精度を高めることは、
そのまま「経営の信頼性」を高めることにつながります。
だからこそ、在庫ズレ対策は現場改善だけでなく、経営改善の一環として取り組む価値があります。
🧾 まとめポイント
- 在庫ズレは「人の問題」ではなく「情報の仕組みの問題」
- エクセル運用ではリアルタイム性・整合性・履歴管理が限界
- クラウド化により、在庫情報を“全員で共有・自動更新”できる環境を整えることが重要
- 在庫精度の向上は、最終的に経営の信頼性を守る施策
🏭 在庫管理のクラウド導入を検討中の方へ
入出庫・棚卸・ロット管理を3日で現場定着できる「アピス在庫管理システム」を詳しくご紹介しています。
※お問い合わせ・お申し込み内容は business@apice-tec.co.jp 宛に届きます。
💡 関連リンク・次に読むべき記事
📘 在庫ズレをなくす第一歩は、“今の在庫管理を見直すこと”から始まります。
あなたの現場に合った仕組みを導入して、ズレのない正確な在庫管理を実現しましょう。
📘 在庫ズレをなくす第一歩 ― クラウドで“仕組み化”する中小企業の現場へ
機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。
アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。
手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)
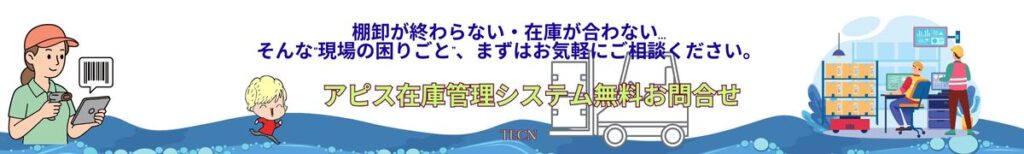
👤 筆者プロフィール|DXジュン(Apice Technology 代表)
「tecn」を運営している DXジュン です。
Apice Technology株式会社の代表として、20年以上にわたり
Web制作・業務改善DX・クラウドシステム開発に携わっています。
普段は企業の現場課題に寄り添いながら、
在庫管理システム/予約システム/求人管理/受発注システム/クラウドソーシング など、
中小企業の仕事を“ラクにするツール”を作っています。
tecn では、業務改善のリアルや、Webシステムの仕組み、 そして「技術が生活をちょっと楽しくしてくれる」ような 日常×デジタルのヒントをゆるく発信しています。
現在の注力テーマは 在庫管理のDX化。 SKU・JAN・棚卸・リアルタイム連携など、 現場で役立つ情報を発信しつつ、 自社のクラウド在庫管理システムも開発・提供しています。
🔗 Apice Technology(会社HP)
🔗 tecn トップページ
🔗 在庫管理システムの機能紹介
記事があなたの仕事や生活のヒントになれば嬉しいです。 コメント・ご相談があればお気軽にどうぞ!

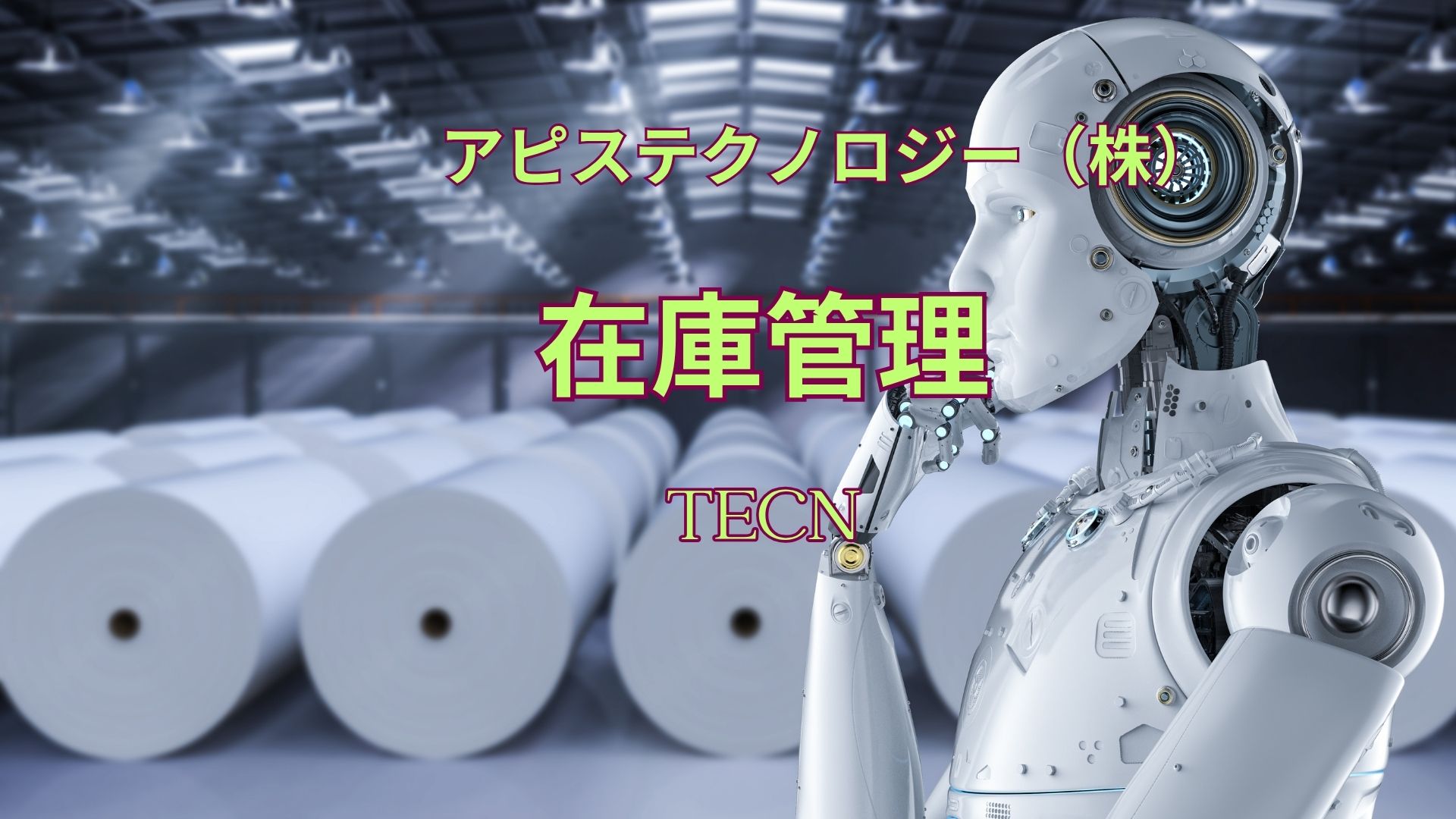





コメント