「同じ商品なのに、JANコードが2つあるのはなぜ?」
中小企業の現場でよく聞く疑問ですが、実はこの仕組みを理解していないと
在庫ズレ・誤出荷・マスタの混乱が起きやすくなります。
JANコードは “売る側の都合で付けられる識別子” のため、
OEM先・販売チャネル・パッケージ違いなどによって
同じ実物なのに複数のJANが存在することは珍しくありません。
一方で、SKUは “実体として同じ商品を管理するための最小単位”。
在庫管理では、このSKUを軸にデータを一つにまとめることで、
複数のJANがあっても在庫が分散しない仕組みを作ることができます。
本記事では、
・JANが複数生まれる理由
・SKUとJANの本質的な違い
・1SKUに複数JANを紐づけるメリット
・現場で使えるSKU⇔JANの対応表の作り方
などを、実務担当者にも分かりやすく解説します。
「JAN違いで在庫が割れてしまう…」という悩みを抱える企業に、
今日から役立つ整理のコツをまとめています。
在庫が合わない、棚卸が終わらない──。
そんな「人手頼みの在庫管理」を根本から変える方法を解説しています。
在庫を仕組みで回すための“第一歩”として、こちらの記事もぜひご覧ください。
機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。
アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。
手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)

【SKU・商品マスタ設計を体系的に学べるピラーガイド】
SKUの決め方から商品属性・JAN・棚番・在庫精度まで、在庫管理の“基礎となる全体像”をまとめています。
H2-1 同じ商品なのにJANが違うのはなぜ?
お店で同じTシャツやイヤホンを見比べてみると、
「見た目はまったく同じなのに、バーコード(JANコード)が違う」
ということがあります。
実はこれは間違いではなく、流通の都合で意図的にJANを分けているケースが多いのです。
ここでは、なぜ同じ商品でもJANが違うのか、その理由をやさしく解説します。
H3-1 OEM・販路・パッケージ違いでJANが分かれる理由
JANコードは「商品ごとに固有の番号」ですが、
その発行単位は“販売形態”や“責任を持つ企業”によって変わります。
つまり、商品そのものは同じでも、流通ルートや販売先が違えば別のJANを付けることがあるのです。
🏭 ① OEM(相手先ブランド)で別JANが付く
メーカーが同じ製品を複数の企業に供給している場合、
それぞれの企業が自社ブランド名で販売するために独自のJANを発行します。
| 販売先 | 商品名 | JANコード | 備考 |
|---|---|---|---|
| メーカー直販 | Tシャツ Mサイズ | 4581234567890 | 自社ブランド |
| OEM先A社 | A社オリジナルTシャツ Mサイズ | 4900000001111 | パッケージとブランド名が違う |
| OEM先B社 | BブランドTシャツ Mサイズ | 4979999002222 | 同じ製品ライン |
中身の生地やサイズは同じでも、販売責任者が異なるため、
それぞれ別のJANが割り当てられます。
🏬 ② 販売チャネル(販路)で別JANを使う
同じメーカーが自社ECサイト・量販店・イベント販売など、
複数の販売経路を持つ場合にも、販路ごとにJANを分けることがあります。
理由は、販売経路ごとの売上集計・在庫引き当てを正確に行うためです。
| 販売チャネル | JANコード | 用途 |
|---|---|---|
| 通常店舗販売 | 4581234567890 | 量販店共通JAN |
| ECサイト | 4900000001111 | ネット通販専用 |
| 直営店 | 4979999002222 | 限定販売用 |
こうしてJANを分けることで、同じSKU(実体商品)でも
「どの販路で、どれだけ売れたか」を分析しやすくなります。
📦 ③ パッケージ変更やリニューアルでJANが更新される
もう一つのよくあるパターンが、「パッケージデザイン変更」や「内容量変更」です。
たとえ中身が同じでも、メーカーの登録上は別商品扱いとなるため、新しいJANを付与します。
- 旧デザイン(JAN:4581234567890)
- 新デザイン(JAN:4900000001111)
小売やECの現場では、どちらも同じ商品として販売されることもありますが、
メーカーのデータベース上では「別JAN=別商品」として管理されています。
H3-2 見た目は違っても中身は同じ“実体商品”
ここまで見てきた通り、
複数のJANが付いていても、中身(製品実体)は同じというケースが多くあります。
たとえば——
- Tシャツの布地やサイズがまったく同じ
- イヤホンの性能・部品構成が全く同一
- 箱のデザインだけ違う
このような場合、在庫として数える単位(SKU)は共通にしておくほうが合理的です。
なぜなら、倉庫や店舗で扱う“実際のモノ”は同じだからです。
💡つまり:
- JANコードは「販売方法や外見の違い」を区別する番号
- SKUコードは「実際のモノ(在庫)」を区別する番号
この考え方に立つと、
「1SKU(在庫単位)」に「複数のJAN(販売経路)」を紐づける意味が見えてきます。
JANの違い=“見せ方や売り方の違い”であって、
SKUの違い=“中身そのものの違い”です。
H2-2 SKUは在庫管理の「最小単位」
商品マスタを整理するうえで、最も重要な概念が「SKU(Stock Keeping Unit)」です。
JANコードとよく混同されますが、実はこの2つは目的も役割もまったく異なります。
ここでは、SKUの本質と、なぜSKUを在庫管理の中心にすべきなのかをやさしく解説します。
H3-1 SKUとJANの本質的な違い
まず整理しておきたいのは、JANとSKUの定義です。
どちらも「商品を識別する番号」ですが、見ている世界が違います。
| 項目 | SKU | JANコード |
|---|---|---|
| 意味 | Stock Keeping Unit(在庫管理単位) | Japanese Article Number(流通識別コード) |
| 目的 | 在庫・販売・補充を“モノの単位”で管理する | 販売・決済・流通の際に識別する |
| 発行主体 | 自社(社内ルール) | GS1協会(企業コード登録制) |
| 管理場所 | 倉庫・店舗・システム内 | レジ・EC・パッケージ |
| 性質 | 実際に存在する「モノ」単位 | 市場に出す「商品」単位 |
つまり、SKUは自社内でモノを見分けるための番号であり、
JANは社外で売るために必要な番号というわけです。
💬 例で考えてみましょう
たとえば、同じ「黒のTシャツ(Mサイズ)」を
自社ブランドでも、OEMブランドでも販売している場合。
- 実際に倉庫にあるTシャツは同じ。だからSKUは1つ。
- でも、販売先が違うため、JANは複数になる。
このように、**“在庫としては1種類、販売上は複数”**という関係が成り立ちます。
ここを混同すると、在庫管理が一気に複雑化してしまうのです。
H3-2 SKUは“モノの実体”、JANは“売り方の識別子”
SKUとJANを一言で区別するなら、こう表現できます。
🧱 SKU=「モノの実体」
🏷 JAN=「売り方の識別子」
同じ商品でも——
- 箱の色が違う
- 販売先が違う
- 販促シールが貼ってある
そんな「売り方の違い」があるたびにJANは増えていきます。
しかし、在庫の現物は変わらない。
倉庫で数えるとき、ピッキングするとき、棚卸するとき、
目の前にあるのは同じ“モノ”であり、それを区別するのがSKUです。
📦 SKUを基準に管理するメリット
- JANが増えても在庫数を一元管理できる
- パッケージ変更・販路追加でも在庫データを使い回せる
- 在庫ズレや重複登録を防止できる
実際の現場では「SKUが在庫を管理する軸」「JANが販売を識別する補助」として使い分けます。
このバランスを理解しておくことで、
“1SKUに複数JANを紐づける設計”がなぜ合理的なのかが見えてくるのです。
在庫が合わない、棚卸が終わらない──。
そんな「人手頼みの在庫管理」を根本から変える方法を解説しています。
在庫を仕組みで回すための“第一歩”として、こちらの記事もぜひご覧ください。
機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。
アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。
手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)

H2-3 なぜ1SKUに複数JANを紐づけるのか?
ここまでの説明で、SKUは“モノそのもの”、JANは“売り方の識別子”であることを理解できたと思います。
では、実際に「1SKUに複数JANを紐づける」設計をとる理由は何なのでしょうか?
この章では、販売チャネル・在庫管理・システム運用の3つの視点から、その仕組みとメリットを解説します。
H3-1 販売チャネルやラベル違いに対応するため
同じ商品でも、販売先やパッケージが違うだけでJANが複数存在するケースがあります。
そのため、SKUを基準にして「同じモノ」をまとめて管理しつつ、JANで販売形態を区別するほうが合理的です。
🏬 例:1SKU(同一商品)に複数JANが付くケース
| SKUコード | JANコード | 販売チャネル | パッケージ |
|---|---|---|---|
| SKU-001 | 4900000001111 | ECサイト用 | 通常箱 |
| SKU-001 | 4900000002222 | 店舗用 | 吊り下げパッケージ |
| SKU-001 | 4900000003333 | ノベルティ用 | 簡易包装 |
この場合、倉庫にある「実際の商品」はすべて同じ。
でも、出荷先・パッケージ・販路が異なるため、販売データ上では別JANとして扱う必要があります。
💡 SKUを中心にして管理すれば、
販売ごとのJANが増えても、在庫の実数はひとつにまとめられるのです。
H3-2 SKUを固定することで在庫ズレを防ぐ仕組み
もし、JANごとに在庫を別管理してしまうとどうなるでしょうか。
- EC用JAN:在庫50
- 店舗用JAN:在庫30
- ノベルティJAN:在庫20
実際の倉庫には100個あるのに、システム上ではバラバラに見えてしまいます。
これが“在庫ズレ”の典型的な原因です。
SKUを固定して「1SKU=1つの在庫」として扱えば、
販売データがどんなに分かれていても、倉庫側では常に在庫数を一元管理できます。
🧮 システムの考え方
- すべてのJANをSKUコードに紐づけて登録
- 受注・販売はJANで処理
- 在庫更新はSKUで処理
これにより、
- JAN単位で販売分析できる
- SKU単位で在庫が常に正しい
という“いいとこ取り”の運用が可能になります。
H3-3 実務で使えるSKU⇔JAN対応表の作り方
複数JANをSKUに結びつけるには、「対応表(マスタ)」を整備するのが効果的です。
下のように、SKUを軸にJANを紐づけることで、どんな販売経路でも同じ在庫を参照できるようになります。
📋 SKU⇔JAN対応表(例)
| SKUコード | JANコード | ブランド | 販売チャネル | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| SKU-001 | 4900000001111 | 自社 | 通販 | 有効 |
| SKU-001 | 4900000002222 | OEM-A社 | 店舗 | 有効 |
| SKU-001 | 4900000003333 | OEM-B社 | 限定セット | 有効 |
| SKU-001 | 4900000000000 | 旧版 | 廃番 | 無効 |
このような対応表をシステムやスプレッドシートで管理しておくと、
- JAN追加時もSKUに紐づけるだけでOK
- 廃番JANを「無効」にするだけで履歴も残る
- データ連携時にJANとSKUの不整合を防げる
といった効果が得られます。
在庫管理システムでは、この仕組みを「JANマスタ」「SKUマスタ」「変換テーブル」などの名称で構築するのが一般的です。
✅ まとめ:1SKUに多JANを紐づける理由
- 同一商品の複数販路・ブランド対応をシンプルに管理できる
- 在庫をSKU単位で統一できるため、ズレが起きにくい
- 販売分析や履歴管理をJAN単位で柔軟に行える
このように、「SKUを在庫の軸、JANを販売の軸」として整理することで、
現場でも経営層でも混乱のない在庫管理が実現できます。
生活にお仕事に、役に立つ関心があるテーマをまとめました。
読んでほしい記事
タブレットでバーコードリーダーを使う方法
H2-4 複数JANを正しく管理するための運用ルール
1SKUに複数JANを紐づける設計を取り入れたとしても、
現場の運用ルールが曖昧だと「JANが混在して在庫がズレる」「旧JANが残る」といった混乱が起きてしまいます。
ここでは、複数JANを正しく扱うために必要な“運用ルール3原則”を紹介します。
H3-1 登録ルールの明確化(代表JAN・無効JANの扱い)
まず大前提として、1SKUの中で「どのJANを代表とするか」を決めておくことが重要です。
同一SKU内に複数のJANが存在する場合、以下のような区分ルールを設定しておくと、後から迷いません。
| 区分 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 代表JAN | 現行・主力として販売されているJAN | 4900000001111(現行商品) |
| 代替JAN | 旧パッケージ・旧販路で使用されていたJAN | 4900000000000(旧版) |
| 無効JAN | 廃番や取扱終了など、現在使われていないJAN | ステータス=無効で登録 |
このルールを明確にしておけば、システム側でも
「代表JANを優先表示」「無効JANは検索対象外」などの設定が可能になります。
また、新JANを追加するときは旧JANを削除せず“無効化”に留めるのが鉄則。
これにより、販売履歴・仕入履歴を正確に追跡できます。
💡 ポイント:削除ではなく「状態フラグで管理する」
→ データ履歴が保持され、会計・販売分析の整合性が保たれる。
H3-2 棚卸・出荷時はSKUで数える
現場で混乱が起きる原因は、
「JAN単位で数えてしまうこと」です。
JANは流通識別コード。
在庫管理の単位はSKUです。
違いを理解するために、具体例を見てみましょう。
✅ ケース①:JAN変更(中身は同じ)
メーカー都合でJANが切り替わったが、中身は同じ。
| SKU | JAN | 理由 | 在庫数 |
|---|---|---|---|
| SKU-001 | 4900000001111 | 旧JAN | 20 |
| SKU-001 | 4900000002222 | 新JAN | 15 |
中身・仕様は同一。
👉 在庫単位はSKU-001で合計35個。
JANで分けると、発注判断が分断されます。
✅ ケース②:出荷時に販路ラベルを貼る
倉庫内は同一商品。
出荷時に「EC用ラベル」「店舗用ラベル」を貼る。
👉 倉庫内では同一SKU
👉 出荷直前に識別
この場合もSKUは1つ。
JANは“出荷識別”であって、在庫単位ではありません。
✅ ケース③:外箱JANが違うが中身は単品管理
6本セット用の外箱JANがあるが、
倉庫では単品で保管している。
👉 在庫管理単位は「単品SKU」
👉 セットJANは販売用コード
この場合もSKUは1つ。
❌ 逆に、SKUを分けるべきケース
ここを入れると理解が一気に深まります。
- パッケージが完全に別
- 販売不可条件が違う
- 返品不可条件が違う
- ノベルティ専用品(販売不可)
👉 これはSKUを分ける
ここを入れないと誤解が出ます。
🔥 最後に締めの一文
SKUは「在庫として区別すべき最小単位」
JANは「流通上の識別コード」
在庫管理では
“数える単位”と“識別する単位”を混同しないことが重要です。
H3-3 分析・販売集計はJANで見る
一方で、販売データや売上分析では逆に、JAN単位の視点が重要になります。
同一SKUでも、販路やブランドによって販売動向が大きく異なるためです。
| JAN | 販売チャネル | 売上数量 | 販売比率 |
|---|---|---|---|
| 4900000001111 | 自社EC | 500 | 60% |
| 4900000002222 | 店舗 | 250 | 30% |
| 4900000003333 | OEM | 100 | 10% |
このようにJAN単位で集計することで、
「どの販路が主力か」「どのパッケージが売れているか」を可視化できます。
在庫管理(SKU)と販売管理(JAN)を分けて考えることで、
“現場の精度”と“経営の分析”を両立できるのです。
✅ まとめ:複数JANを正しく扱う3原則
- 登録ルールを決める(代表・代替・無効を区別)
- 在庫管理はSKUで統一する(現物の数を基準)
- 販売分析はJANで行う(販路・市場の動きを見る)
これらを明文化し、商品マスタの運用ルールとして定着させることで、
どんな販路拡大やリニューアルがあっても、在庫の“ひとつの真実”を維持できます。
生活にお仕事に、役に立つ関心があるテーマをまとめました。
H2-5 まとめ|「在庫の単位=SKU」で混乱をなくす
在庫が合わない、棚卸が終わらない──。
そんな「人手頼みの在庫管理」を根本から変える方法を解説しています。
在庫を仕組みで回すための“第一歩”として、こちらの記事もぜひご覧ください。
機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。
アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。
手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)

ここまで解説してきた「1SKUに複数JANを紐づける」考え方の本質は、
在庫をどの単位で捉えるかという一点に集約されます。
この考え方を理解しておくと、JANが増えても、販路が増えても、在庫管理の軸はブレません。
H3-1 JANは流通用、SKUは管理用と覚えよう
JANコードとSKUは似ているようで、まったく異なる目的を持っています。
もう一度整理すると——
| 観点 | JANコード | SKUコード |
|---|---|---|
| 役割 | 商品を“販売・流通”のために識別 | 商品を“在庫管理”のために識別 |
| 管理範囲 | 流通・POS・ECなど社外向け | 倉庫・店舗・システムなど社内向け |
| 発行元 | GS1協会(外部登録) | 自社で自由に設計 |
| 対象 | パッケージ・販路・ブランドごと | モノの実体(色・サイズ・型番など) |
💡 覚え方
- JAN=「売るための番号」
- SKU=「数えるための番号」
どんなに多くのJANがあっても、SKUが正しく定義されていれば、
在庫の整合性は必ず保てます。
逆に、SKUが定義されていない状態では、JANが1つでも管理は破綻します。
H3-2 SKUを軸にすれば複数JANも怖くない
SKUを在庫の中心に据えることで、
複数JANがあっても次のような運用が可能になります。
📦 実務的なメリット
- 在庫はSKU単位で常に正確
→ JANの増減や販路拡大にも影響されない - 販売履歴はJAN単位で柔軟に分析
→ 「どのパッケージが売れているか」が一目で分かる - システム連携が容易
→ POS、EC、倉庫、基幹システムの間で整合性が取れる
つまり、**在庫の世界ではSKUが“真実の在り処”**なのです。
JANはあくまで「売り方を区別するためのラベル」にすぎません。
✅ 結論
- 在庫の単位は常に「SKU」で統一する
- JANはSKUに紐づける補助コードとして扱う
- SKUを軸にマスタを整備すれば、複数JANも管理できる
こうした考え方をシステムや現場に浸透させることで、
在庫の混乱を防ぎ、「一つのSKU=一つの在庫真実」を維持できます。
📚 次に読むべき関連記事
- SKUとは?在庫と販売をつなぐ“最小単位”をやさしく解説
- JANコードと社内コードの使い分け方|商品マスタ統一のベストプラクティス
- 商品コード設計の基本|色・サイズバリエーション管理の鉄則
- タブレットでバーコードリーダーを使う方法|在庫管理での実用ラインを解説 |
👤 筆者プロフィール|DXジュン(Apice Technology 代表)
「tecn」を運営している DXジュン です。
Apice Technology株式会社の代表として、20年以上にわたり
Web制作・業務改善DX・クラウドシステム開発に携わっています。
普段は企業の現場課題に寄り添いながら、
在庫管理システム/予約システム/求人管理/受発注システム/クラウドソーシング など、
中小企業の仕事を“ラクにするツール”を作っています。
tecn では、業務改善のリアルや、Webシステムの仕組み、 そして「技術が生活をちょっと楽しくしてくれる」ような 日常×デジタルのヒントをゆるく発信しています。
現在の注力テーマは 在庫管理のDX化。 SKU・JAN・棚卸・リアルタイム連携など、 現場で役立つ情報を発信しつつ、 自社のクラウド在庫管理システムも開発・提供しています。
🔗 Apice Technology(会社HP)
🔗 tecn トップページ
🔗 在庫管理システムの機能紹介
記事があなたの仕事や生活のヒントになれば嬉しいです。 コメント・ご相談があればお気軽にどうぞ!


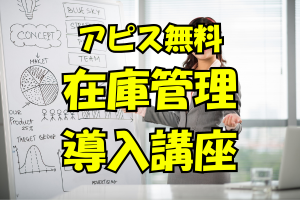





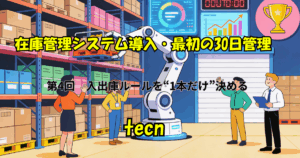
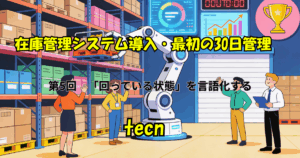
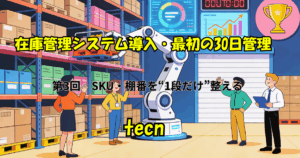
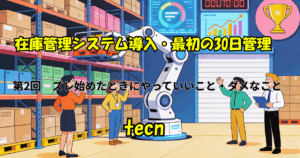
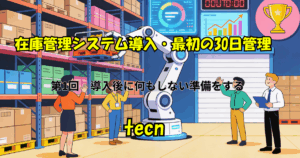




コメント