50商品を探す時間を半減!棚番ルールを整える|倉庫の見える化と効率化の基本 |在庫管理 B-1
在庫が合わない、棚卸が終わらない──。
そんな「人手頼みの在庫管理」を根本から変える方法を解説しています。
在庫を仕組みで回すための“第一歩”として、こちらの記事もぜひご覧ください。
機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。
アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。
手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)

H2-1 なぜ“棚番ルール”が在庫管理の要なのか
倉庫の現場で最も多いムダ――それは「探す時間」です。
商品がどこにあるのかを確認するために歩き回り、
担当者によって置き場所の認識が異なることで、在庫のズレや誤出荷が発生します。
この“探すムダ”をなくす第一歩が、棚番ルールの整備です。
H3-1 “どこにあるかわからない”が引き起こす時間ロス
多くの中小倉庫では、「あの辺りにある」「あの棚の右側」といった曖昧な指示で在庫を管理しています。
その結果、1つの商品を見つけるのに数分〜十数分かかるケースも珍しくありません。
1回あたり数分のロスでも、1日で数十回のピッキング作業が発生すれば、
1人あたり1時間以上のロスになります。
しかも、担当者が変わるたびに「場所の再確認」から始まるため、教育にも余計な時間がかかります。
棚番ルールは、この「探す」という無駄な行為を根本からなくし、
誰が見ても一瞬で場所を特定できる倉庫を実現します。
H3-2 探す時間=コストロスとヒューマンエラーの温床
「探す時間」は単なる時間ロスではなく、コストロスとヒューマンエラーの温床でもあります。
- 探す間にピッキング順序が乱れる
- 焦って似た商品を誤って取る
- 在庫数を手入力で修正し忘れる
このようなミスが積み重なると、
現場では「数は合っているのに出荷できない」「在庫があるはずなのに見つからない」といった混乱が起こります。
つまり、棚番を整備しない状態は、管理の属人化と誤出荷リスクを常に抱えた状態。
“探す時間”の背後には、企業の生産性と信頼性を下げるコストが潜んでいます。
H3-3 整理整頓ではなく「識別ルール化」でミスを防ぐ
「棚番ルール」というと、単なる整理整頓や5S活動の延長だと誤解されがちです。
しかし実際は、**倉庫をデータで管理するための“識別ルール化”**です。
例えば、
- エリアごとにアルファベット(A・B・C)を割り当てる
- 棚番号を連番化し、上段から下段へ規則的に付番する
- 段・列を統一フォーマット(例:A-03-2)で表記する
といったルールを設ければ、誰でも同じ表現で場所を特定できます。
つまり、棚番は単なる番号ではなく、**「現場の言語」と「システムのキー項目」**を兼ねる存在なのです。
この識別ルールを徹底すれば、探す時間をゼロに近づけ、
新人でもベテランでも同じ精度で在庫を扱える“標準化倉庫”が実現します。
H2-2 棚番(ロケーションコード)の基本構造
棚番とは、倉庫内で商品が保管されている場所を一意に識別するための「住所」です。
「どこに何があるか」を誰でも瞬時に把握できるように、エリア・棚・段の3階層で整理するのが基本。
この仕組みを整えることで、ピッキング効率が飛躍的に上がり、在庫の見える化も進みます。
H3-1 エリア・棚・段の3階層で考える「住所化」の考え方
倉庫を効率的に管理するには、空間を“階層的に分ける”ことが重要です。
一般的に、次の3つの階層で棚番(ロケーションコード)を構成します。
| 階層 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| エリア | 倉庫内のゾーン区分(例:A倉庫、B倉庫など) | A |
| 棚番号 | 棚ごとの識別番号 | 03 |
| 段番号 | 棚の上から何段目かを表す | B2 |
このように3階層で管理すれば、倉庫全体が地図のように整理され、
「Aエリアの3番棚の2段目」といった形で、瞬時に在庫場所を特定できます。
これが“倉庫を住所化する”という発想です。
H3-2 例:A-03-B2 で表す“倉庫内の住所”とは?
実際の棚番コード「A-03-B2」は、次のように読み解けます。
- A:倉庫エリア(例:第1倉庫、左ブロックなど)
- 03:棚番号(3番目の棚)
- B2:B段の2列目、または棚の中段
つまり、Aエリアの3番棚・中段B2 に商品があるという意味です。
このような表記をルール化することで、誰が見ても同じ認識で場所を特定できます。
さらに、コード形式をシステムのマスタ項目と連携させれば、在庫検索や出荷指示も自動化が可能になります。
H3-3 数字+アルファベットを使い分けるルール設計のコツ
棚番のルール設計では、「人にわかりやすく」「システムでも扱いやすい」ことがポイントです。
そのため、アルファベットはエリアや段などの識別に、数字は順番や位置に使うのが効果的です。
例:A-05-3
→ 「Aゾーン・5番棚・3段目」
このようにルールを明確化しておくと、棚が増えても混乱せず、
将来的な倉庫拡張やレイアウト変更にも柔軟に対応できます。
また、ハイフン(-)を統一的に使用して階層を区切ることで、
システム連携時も認識しやすく、誤登録を防ぐことができます。
H2-3 棚番ルール整備のステップ【現場導入編】
棚番ルールは「決める」だけでは意味がありません。
重要なのは、現場で迷わず使えるように定着させることです。
ここでは、棚番ルールを実際の倉庫に導入していく4つのステップを紹介します。
H3-1 ステップ①:棚・区画の命名ルールを決める
まず最初に行うのは、「棚をどう呼ぶか」というルールの設計です。
曖昧な呼称をなくし、誰が見ても一貫性のある命名を行うことで、
後のラベル発行・システム登録・ピッキング指示がすべてスムーズになります。
命名時のポイント:
- エリア(ゾーン)ごとにアルファベットを付与(例:A・B・C)
- 棚番号は左から右、奥から手前の順に連番
- 段番号は上から下へ数字で表現
例:「A-03-2」=Aゾーンの3番棚・2段目。
このルールを明文化し、倉庫全体マップに一覧化しておくと、
新しい棚を追加する際も迷わず付番できます。
H3-2 ステップ②:ラベル発行と棚表示の統一
ルールを決めたら、次は“誰でも認識できる可視化”です。
棚番を明示するラベルを印刷し、棚の見やすい位置(右上または中央)に貼り付けます。
ポイント:
- フォントサイズは3〜5m離れても読める大きさ
- 英字・数字・ハイフンを明確に区切る
- 色や枠を使ってゾーンごとの識別を容易にする
また、棚ラベルのデザインを全エリアで統一することも重要です。
異なるフォーマットが混在すると、現場の混乱や誤認を招く原因になります。
H3-3 ステップ③:入庫時の登録と出庫時の照合を習慣化
棚番ルールを定着させるには、運用に組み込むことが欠かせません。
運用ルール例:
- 入庫時に「棚番コード」を在庫システムへ登録
- 出庫時は、伝票またはハンディ端末で棚番をスキャンし照合
- 在庫移動時は「旧→新ロケーション」を記録
このように、棚番を常に入出庫の基準にすれば、
「商品がどこにあるかわからない」「出荷済みか不明」といった問題は大幅に減少します。
棚番は“表示物”ではなく、“データ管理のキー”と認識することがポイントです。
H3-4 ステップ④:システム・アプリに棚番情報を紐づけ
最後のステップは、棚番情報をシステムへ反映させることです。
在庫システムや販売管理ソフトに、棚番(ロケーションコード)をマスタ項目として登録します。
実践のコツ:
- 在庫マスタに「棚番」フィールドを追加
- ピッキングリストに棚番を自動表示
- 棚番変更時は履歴を残す仕組みを導入
最近では、スマホアプリやクラウド在庫管理ツールでも棚番登録が可能です。
QRコードを使えば、現場で商品をスキャンするだけで「場所・数量・担当者」が紐づくため、
リアルタイム在庫更新が簡単に実現します。
このように、ルール → 可視化 → 運用 → システム連携 の順で進めることで、
棚番管理が倉庫全体の“基盤データ”として機能し始めます。
在庫が合わない、棚卸が終わらない──。
そんな「人手頼みの在庫管理」を根本から変える方法を解説しています。
在庫を仕組みで回すための“第一歩”として、こちらの記事もぜひご覧ください。
機能はシンプル。でも、使えば業務効率がぐんと上がる。
アピス在庫管理 ― 小規模事業者・店舗のための“ちょうどいいDX”。
手作業から脱却し、在庫の見える化を実現しよう。 アピステクノロジー(株)

H2-4 棚番管理をクラウド化すると何が変わるか
棚番ルールを整えても、「情報が現場に届くのが遅い」状態では効果が半減します。
そこで注目すべきが、棚番管理のクラウド化。
リアルタイムに「どこに何があるか」が共有できることで、倉庫の運営が“データドリブン”に変わります。
H3-1 リアルタイムで“どの棚に何があるか”を可視化
クラウド在庫システムを導入すると、
「A-03-2に残り3個」「B-05-1は入荷済み」など、在庫状況がリアルタイムで確認できます。
これは、各棚番に在庫データをひもづけてクラウド上で一元管理する仕組み。
現場・事務所・経営層が同じ情報を同時に見られるため、
在庫確認・指示・発注判断のスピードが圧倒的に向上します。
また、在庫変動が即座に反映されるため、
「もう出荷済みだった」「在庫がないと思って発注した」などの二重処理も防げます。
H3-2 スマホ・タブレットから検索できる仕組み
クラウド化の最大の強みは、端末を選ばない運用です。
スマホやタブレットから棚番を検索すれば、
どの棚にどの商品があるかが即座に分かります。
例:
- 商品名を入力 → 棚番が表示(A-04-1)
- 棚番を入力 → 在庫数量・ロット情報を表示
これにより、
・新人でもすぐに倉庫を回せる
・事務所からでも在庫を把握できる
・外出先からでも確認・指示が可能
といった“現場を選ばない管理”が実現します。
特に多拠点倉庫や店舗間で在庫を融通している企業では、
クラウド棚番管理が“社内共通の言語”として機能します。
H3-3 在庫移動・ロット・期限などの情報も紐づけ可能
クラウド棚番管理では、棚番に紐づけられるのは「場所」だけではありません。
システム上では、棚番1つに以下のような情報を付与できます。
| 項目 | 内容例 |
|---|---|
| ロット番号 | 生産・仕入れごとの識別 |
| 期限情報 | 賞味期限・使用期限など |
| 入庫日・出庫日 | 履歴管理・棚卸対応 |
| 担当者 | 誰がどの棚を操作したか |
このように、**棚番が在庫データの“軸”**となることで、
品質管理・トレーサビリティ・在庫精度が飛躍的に向上します。
また、データをエクスポートすれば、販売管理・会計ソフトとの連携も容易になり、
棚番がそのまま「在庫連携のキー情報」として活用できます。
H2-5 運用でつまずかないための注意点
- H3-1 現場が使わないルールは“形骸化”する
- H3-2 棚番更新・移設時の再ラベル化ルールを決める
- H3-3 システム変更時は棚番データの整合を確認
H2-5 運用でつまずかないための注意点
棚番管理は「導入したら終わり」ではありません。
むしろ、現場が使い続けてこそ価値が生まれる仕組みです。
ここでは、ルール定着を阻む3つのつまずきポイントと、その回避方法を紹介します。
H3-1 現場が使わないルールは“形骸化”する
最も多い失敗が、「決めたルールを誰も使っていない」状態です。
原因の多くは、ルールが現場の実態に合っていないこと。
たとえば、
- 棚番コードが長すぎて入力が面倒
- 棚ラベルの位置が見づらく、読み間違える
- 新人が覚えきれず、勝手に略称を使う
こうした小さな不便が積み重なると、ルールは形骸化します。
運用を定着させるには、現場スタッフが使いやすい設計を優先することが重要です。
さらに、定期的に「現場ヒアリング」を行い、
「使いにくい」「見づらい」といった声を吸い上げて、
ルールをアップデートできる運用体制を整えておきましょう。
H3-2 棚番更新・移設時の再ラベル化ルールを決める
棚番ルールを導入しても、倉庫のレイアウト変更や棚の移動が発生します。
このとき、「新しい棚だけ手書きでラベルを貼った」などの運用をすると、
あっという間に整合性が崩れます。
再ラベル化のルールは、以下のように明確にしておきましょう。
再ラベル運用の基本:
- 移設・新設が発生したら即申請(申請者と承認者を明確に)
- ラベル発行担当を決めておく(現場で勝手に作らない)
- 旧ラベルは必ず撤去し、写真で更新後を記録する
また、棚番変更を行った場合は、
在庫システム上の棚番データを同時に更新しなければ、
「現物とデータが不一致」になるリスクが高まります。
H3-3 システム変更時は棚番データの整合を確認
在庫管理システムや販売管理ソフトをリプレースする際、
もっとも注意すべきは「棚番データの引き継ぎ漏れ」です。
よくある失敗例:
- 新システムでは棚番項目がなく、CSV移行時に削除された
- 棚番コードの桁数制限が違い、一部が切り捨てられた
- 新旧の棚番体系が混在して、検索が機能しなくなった
これを防ぐには、移行前に棚番マスタを単独でエクスポートし、
旧システムと新システムでサンプル照合テストを実施することが重要です。
特に、棚番を在庫・ロット・取引履歴に紐づけて運用している場合は、
「棚番がズレる=在庫情報が壊れる」に直結します。
システム更新時には、必ず「棚番コード整合チェックリスト」を作成し、
IT担当・現場リーダーのダブルチェックで確実に整合を取るようにしましょう。
H2-6 まとめ|棚番ルール整備は「探さない倉庫」への第一歩
倉庫業務の生産性を上げる最大のポイントは、
「探す時間を減らす」ことにあります。
棚番ルールを整備し、マップ化・クラウド化を進めれば、
“誰が作業してもすぐに目的の商品にたどり着ける倉庫”が実現します。
これは単なる整理整頓ではなく、情報を見える化する経営改善です。
H3-1 探す時間を半減する=生産性を倍増する
倉庫で商品を探す時間は、日々の業務の中で大きなロスになっています。
1回あたり数分でも、1日100件の出荷があれば、数時間単位のムダです。
棚番ルールを整えることで、
「どの棚に何があるか」が一瞬で分かるようになり、
ピッキング・補充・棚卸のすべてがスピードアップします。
結果として、作業時間を半減=生産性を倍増することも十分に可能です。
特に中小規模の倉庫では、人数を増やさずに出荷能力を上げる最も効果的な方法といえます。
H3-2 “誰でも探せる倉庫”が属人化をなくす
棚番・マップ・クラウド管理を整備すれば、
「この人しか分からない」「ベテランがいないと出荷できない」という属人化を解消できます。
新人や派遣スタッフでも、ルールとマップを見れば作業できる。
それが“探さない倉庫”の理想形です。
属人化をなくすことで、教育時間が減り、
欠員時のリスクも小さくなり、全体のチーム力が安定します。
倉庫の整備とは、実は“人材マネジメントの効率化”でもあるのです。




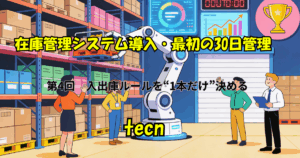
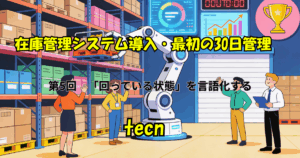
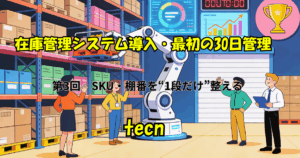
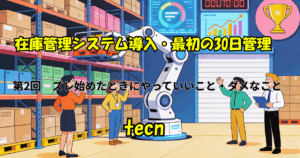
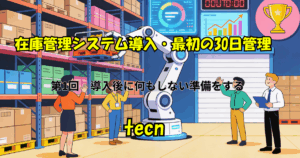




コメント